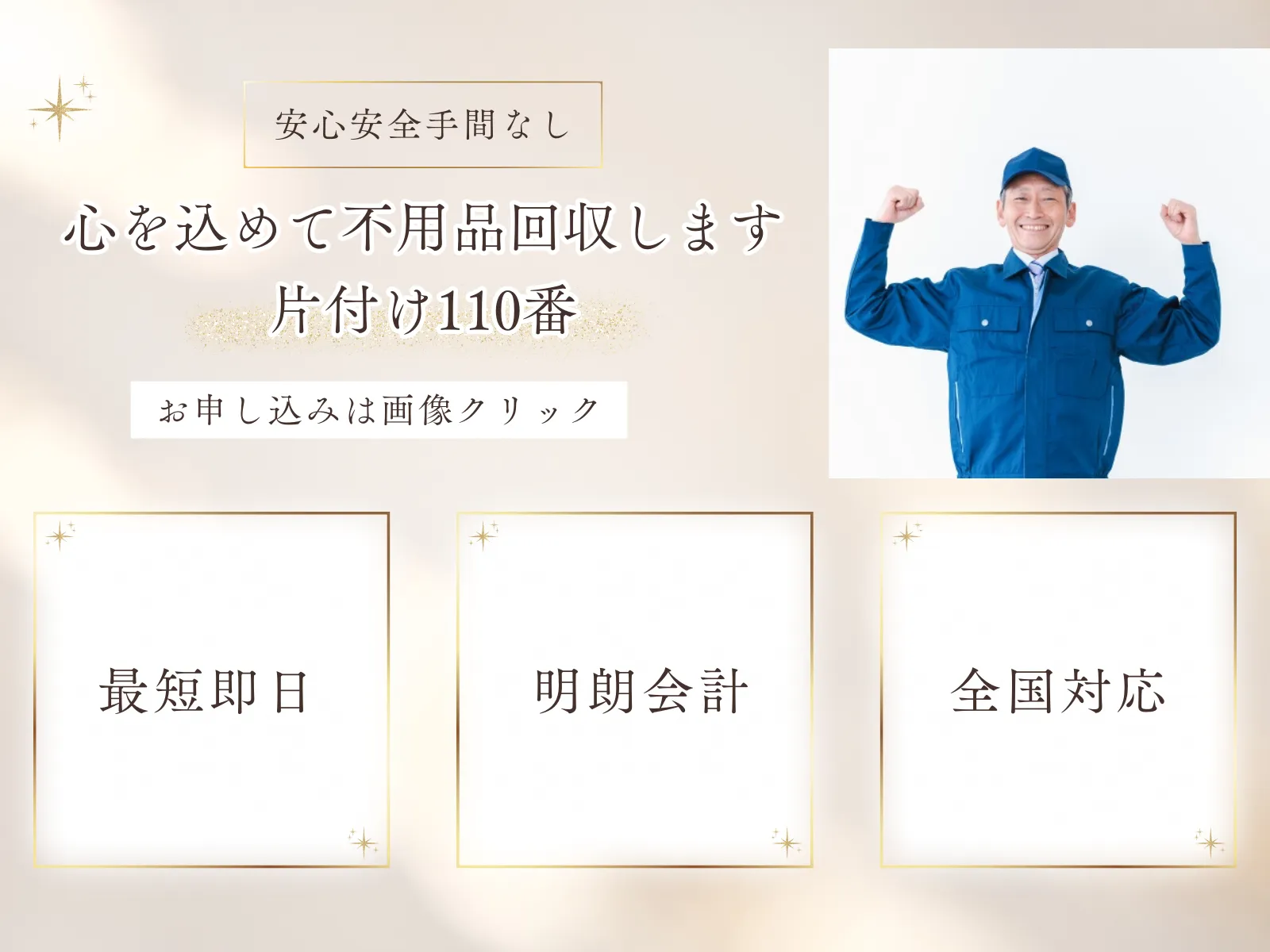夏の夜を彩る花火は、その美しさと楽しさで多くの人々を魅了します。しかし、楽しんだ後の花火の後片付けに困っている方も多いのではないでしょうか?特に、花火の正しい捨て方がわからず、そのまま放置してしまうこともあるかもしれません。実際に、手持ち花火、ロケット花火、打ち上げ花火など、それぞれの花火には異なる処分方法が求められます。誤った処分方法を取ると、火災や爆発のリスクがあり、非常に危険です。
この記事では、花火を安全かつ確実に処分するための方法を詳しく解説します。花火の捨て方に関する正しい知識を身につけることで、安心して花火を楽しんだ後も、安全に片付けることができます。特に、自治体の回収ルールや回収業者の利用方法、未使用・使用済みの手持ち花火の具体的な処理手順について詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてください。
さあ、この記事を読んで、花火を楽しんだ後の片付けも完璧にこなしてみましょう。
未使用花火が手元に残る理由
花火は夏の風物詩として家族や友人との楽しい時間を彩ってくれますが、実際には「買ったけれど使わなかった花火が残ってしまった」という経験を持つ人も少なくありません。ここでは、未使用の花火が手元に残る主な理由を紹介します。
1. 天候不良や突然の雨
もっとも多い理由の一つが、急な天気の変化による中止です。特に夏場は夕立や雷雨が多く、「準備したけれどできなかった」というケースがよくあります。風が強い日も安全上の理由で使用を控える必要があり、結果的に花火が使われずに残ることになります。
2. 使用制限や禁止場所の増加
近年、住宅密集地や公共の場所では花火の使用が禁止または制限されているエリアが増加しています。せっかく購入しても、予定していた場所で使えずに持ち帰ることになったという例も少なくありません。音や煙、火の粉などのトラブル防止のため、ルールを守る意識が高まっているのも背景にあります。
3. 子どもや高齢者の体調不良
家族イベントとして花火を計画していたが、子どもや高齢の親族の体調が悪くなり中止したという事情もよくあるケースです。特に夜間の屋外での活動は体力を使うため、体調を考慮して予定を変更することも多いようです。
4. 購入量が多すぎた
楽しみにしすぎて「多めに買ってしまった」「セットで買ったけれど全部使い切れなかった」ということもよくあります。特に詰め合わせパックや福袋タイプの商品は量が多めに設定されているため、残りやすい傾向があります。
5. 花火大会やイベントの中止
地域の花火大会や自治会のイベントなどで使う予定だったものの、社会情勢や安全上の都合で中止になったというケースもあります。近年は感染症や災害の影響でイベントが急にキャンセルされることも増え、使用されずに残った花火が家庭に保管されている例も多く見られます。
自治体処分できるのは「手持ち花火」のみ

手持ち花火は比較的小型で、火薬の量も少ないため、燃え尽きた後の処理が比較的安全です。自治体のごみ収集作業員が扱う際のリスクも低く抑えられます。一方、ロケット花火や打ち上げ花火は、大型で火薬の量も多いため、残った火薬が発火するリスクが高く、処理が困難です。これらの花火は爆発や火災の原因となりやすいため、専門的な知識と設備が必要です。多くの自治体のごみ処理施設は、一般家庭から出る普通の可燃ごみを処理する設備が整っています。手持ち花火は、適切な手順(例:水に浸して冷却)を踏めば、他の可燃ごみと一緒に安全に処理できます。
ロケット花火・打ち上げ花火は回収業者に依頼しよう
日本では、花火に関する法律や規制が厳しく定められています。手持ち花火は家庭用の小型花火として、比較的簡単に取り扱えるように規制されていますが、ロケット花火や打ち上げ花火はその規制が厳しく、処理も専門的な業者に依頼することが推奨されています。ロケット花火や打ち上げ花火は、特殊な廃棄物として扱われるため、一般的なごみ処理施設では対応できないことが多いです。これらの処分には、専用の設備や処理技術が求められます。
未使用・使用済みの手持ち花火の捨て方

それでは実際に、家庭用手持ち花火の捨て方について解説します。
手順(1)1週間水に浸す
使用済みの手持ち花火には、燃え尽きていない火薬や火種が残っていることがあります。そのまま捨てると、ゴミ袋の中で発火する可能性があります。そこで、まず花火を十分な水に浸しておくことが重要です。
1.バケツや水を張った容器を用意。使用済みの花火が完全に浸かるサイズの容器を用意します。
2.花火を水に浸す。 花火を容器に入れ、水をたっぷり注ぎます。
3.1週間そのままにする。少なくとも1週間はそのまま放置します。これにより、花火内部の火薬が完全に湿り、発火のリスクがなくなります。
手順(2)燃えるゴミに出す
花火が十分に水に浸かった後は、火薬が湿り、発火のリスクが低くなります。この状態であれば、一般的な燃えるゴミとして処分することができます。1週間水に浸けた花火を取り出し、余分な水を切ります。完全に乾かす必要はありませんが、水が滴らない状態にします。花火を燃えるゴミ用の袋に入れます。他の可燃ごみと一緒にしても問題ありません。自治体の指定する燃えるゴミの回収日に、通常のゴミと一緒に出します。
注意点(1)自治体によっては回収を受け付けていない場合も
自治体によっては、花火を燃えるゴミとして回収しない場合があります。そのため、事前に確認することが重要です。各自治体のホームページやゴミ分別ガイドラインをチェックしましょう。
注意点(2)正しく処理しない場合残った火薬が発火して爆発や火災の原因に
花火を正しく処理しないと、残った火薬が発火し、爆発や火災の原因となる危険性があります。特に、使用済みと思われる花火でも、内部に未燃焼の火薬が残っていることがあります。ゴミ袋の中で火薬が発火すると、他のゴミに燃え移り、火災になる危険があります。閉じた空間で発火すると、ガスや熱の急激な膨張により爆発が起こる可能性があります。不安がある場合は、専門の不用品回収業者に依頼することも検討しましょう。
花火の種類別の処分方法
花火はその種類によって構造や火薬量が異なるため、処分方法も一律ではありません。誤った方法で処分すると、火災やケガなどの事故につながる恐れもあります。ここでは、手持ち花火・噴出花火・打ち上げ花火など、主要な種類ごとの正しい処分方法を分かりやすく紹介します。
手持ち花火の処分方法
もっとも一般的な家庭用花火である手持ち花火は、適切に処理すれば家庭ごみとして処分可能な自治体が多いです。
【処分手順】
-
バケツに水を張り、花火を1〜2日間しっかり水に浸ける(火薬が湿って着火しなくなるまで)。
-
水から引き上げて水気をよく切り、紙や新聞紙で包む。
-
各自治体のごみ分別ルールに従って、可燃ごみまたは不燃ごみとして処分。
※火薬が乾いてしまうと再着火の危険があるため、処分直前まで水に浸しておくことが推奨されています。
噴出花火・ねずみ花火などの回転型・置き型花火
噴出タイプや回転型の花火は火力が強く、構造も複雑なため、処分時の注意が必要です。
【処分手順】
-
手持ち花火と同様、水に1〜2日しっかり浸けてから処分。
-
特に大きめのものは、火薬が深部にあるため、分解せずそのまま水没処理を行うのが安全です。
打ち上げ花火・ロケット花火の処分方法
これらは火薬量が多く、誤って発火すると重大な事故につながるため、家庭での処分は推奨されていません。
【処分方法】
-
自治体に相談のうえ、危険ごみとして回収してもらう。
-
または、花火販売業者や専門の処理業者に引き取りを依頼。
※天筒型・筒状の打ち上げ花火は、水に浸しても内部まで水が届かないことがあるため、自己処分は危険です。
花火のパッケージやセット品の処分
未使用の詰め合わせセットや残ったパッケージ品も、中身を取り出して個別に処分することが基本です。
-
外箱や包装は資源ごみとして分別。
-
花火本体は前述のとおり、種類別に水に浸してから処分。
未使用花火をそのまま保管するリスク
使わずに残った花火を「また来年使えばいい」とそのまましまい込んでいませんか? 実は、花火は長期保管に向いていない“火薬製品”であり、放置することでさまざまなリスクが生じます。ここでは、未使用の花火を保管し続けることで起こりうる危険について詳しく解説します。
1. 火災の原因になる可能性
花火には火薬が含まれているため、高温・多湿な場所や直射日光が当たる環境に放置しておくと、自然発火や爆発のリスクがゼロではありません。とくに夏場の物置や車内などでは気温が急上昇するため、危険性が増します。
2. 劣化による不発・誤作動のリスク
長期間保管された花火は、湿気や経年劣化によって着火しにくくなったり、予期しない動作を起こす可能性があります。火がつかないからといって何度も火を近づけたりすると、突然爆発するケースも報告されています。
3. 子どもの誤使用やいたずらによる事故
家庭内に花火が置かれていると、子どもが興味本位で触ってしまう危険があります。特に封を開けた状態の花火は中身が見えており、簡単に取り出せてしまうため、誤って着火したり、室内で遊んでしまうリスクがあります。
4. 虫や湿気による汚損・変質
保管状態によっては、包装に穴があいたり、火薬部分にカビや湿気がしみ込むなどして、使用不能になるケースも少なくありません。さらに、火薬に引き寄せられた虫が入り込むこともあり、見た目にも衛生的にも問題が出ることがあります。
5. 保管忘れによる「放置ゴミ」化
花火は意外と小さく、収納棚や納戸の奥にしまうとそのまま忘れがちです。時間が経ってから存在を思い出し、処分に困ることも多く、自治体への問い合わせが急増する原因にもなっています。
花火の自治体の処分ルールの確認をしよう
未使用の花火を処分したいと思ったとき、「普通ごみで出していいの?」「水に浸すって本当?」と迷う方は少なくありません。実は、花火の処分方法は自治体によって分類や手順が異なり、全国一律ではないのが実情です。安全かつ正しく処分するためには、必ずお住まいの自治体のルールを確認することが大切です。
自治体によって異なる「ごみの分別」
花火は火薬を含む製品のため、可燃ごみに出せる地域もあれば、不燃ごみや危険ごみに分類される自治体もあります。たとえば、
-
山口市では、未使用花火を水に浸してから「燃やせるごみ」として処分可能
-
浜松市では、「燃えるごみ」として扱うが、必ず水に数日間浸してから捨てるよう指導
-
横浜市では、「燃やすごみ」だが未使用のまま捨てるのは不可で、事前の水浸しが必須
このように、花火の扱いは地域ごとに違いがあり、自己判断で処分すると思わぬトラブルを招くこともあります。
処分前に確認しておきたいポイント
処分を始める前に、次の項目を自治体の「ごみ分別ガイド」や公式ホームページでチェックしましょう。
-
花火は「可燃」「不燃」「危険ごみ」のどれに分類されているか
-
水に浸す必要があるか、浸す時間はどのくらいか
-
使い切れなかった未開封の花火はどうするべきか
-
ゴミ袋に入れる際の注意点(新聞紙で包むなど)
不明な場合は、自治体のごみ収集課や市民相談窓口に問い合わせるのが確実です。
安全な処分は地域ルールの遵守から
たとえ家庭用の小さな手持ち花火であっても、火薬類である以上、安全に処理するためには地域のルールを守ることが不可欠です。処分方法を間違えると、発火やごみ収集時の事故につながる可能性もあるため、正しい情報を確認したうえで処理しましょう。
花火の保管と使用期限について
花火は夏のレジャーに欠かせないアイテムですが、使い切れずに翌年まで持ち越すことも珍しくありません。しかし、花火は“火薬類”であることを忘れてはいけません。誤った保管方法や長期保存によって、思わぬ事故につながることもあるため、正しい知識を持っておくことが大切です。ここでは、花火の適切な保管方法と使用期限の目安について解説します。
花火に使用期限はあるの?
市販の花火には明確な「使用期限」は表示されていないことが多いですが、安全に使用できる目安は「購入から1~2年以内」とされています。火薬は湿気や温度の影響を受けやすく、経年劣化によって発火性能が低下したり、予期せぬ動作をすることもあります。
特に長期間保管された花火は、
-
火がつかない(不発)
-
火花の出方が通常と異なる
-
想定外の方向に飛ぶ
といったトラブルが報告されています。10年以上前の古い花火を不用意に使用するのは非常に危険です。
花火の正しい保管方法
花火を安全に保管するには、以下のポイントを押さえることが重要です。
-
直射日光の当たらない場所で保管する
高温になる場所(車内・ベランダ・屋根裏など)では火薬が不安定になりやすく、自然発火の危険があります。 -
湿気の少ない、風通しの良い場所を選ぶ
湿気を吸収すると火薬が劣化しやすくなるため、押入れや納戸などの乾燥した場所に保管するのが理想です。 -
密閉容器やビニール袋は避ける
密閉状態で湿気がこもるとカビや結露の原因になるため、通気性のある紙袋や箱に入れて保管するのがベターです。 -
子どもの手の届かない場所に置く
万が一の誤使用を防ぐため、保管場所には注意しましょう。
保管に不安があるなら、早めの処分を
もしも「どこに保管したか忘れた」「湿気が入り込んだかもしれない」といった不安がある場合は、無理に使用せず、適切な方法で処分することをおすすめします。特に見た目に変化がある花火(変色・カビ・紙の膨張など)は使用を控えてください。
大量の花火、ロケット花火、打ち上げ花火の処分は不用品回収業者を利用しよう

不用品回収業者は、花火の取り扱いや処分に関する専門知識と技術を持っています。特に、ロケット花火や打ち上げ花火は、大量の火薬を含むため、素人が扱うと非常に危険です。業者は適切な処理方法を知っているため、安全に処分できます。また、大量の手持ち花火を個別に処理するのは非常に手間がかかります。業者に依頼することで、一度に大量の花火を効率的に処分できます。さらに、自治体によっては、大量の花火を家庭ごみとして出すことが制限されている場合があります。しかし、不用品回収業者を利用することで、安全性、法的な適合性、便利さ、効率、そして環境への配慮の観点から、花火の処分を安心して行うことができます。不用品回収業者のメリットデメリットについては、「不用品回収業者を利用するメリットデメリット~業者選びのコツまで徹底解説」をあわせてご覧ください。
まとめ:花火を正しく安全に処分しよう

花火の捨て方に困っている方に向けて、この記事では安全かつ正確な花火の処分方法を解説しました。手持ち花火は自治体のルールに従い、1週間水に浸した後に燃えるゴミとして出すことが推奨されます。しかし、自治体によっては回収を受け付けていない場合もあるため、事前確認が必要です。また、大量の手持ち花火やロケット花火、打ち上げ花火は不用品回収業者に依頼することが安全で効率的です。専門業者は適切な処理方法を知っており、法的な規制にも対応しています。この記事を参考にして、花火を正しく安全に処分し、安心して花火のシーズンを楽しみましょう。
花火の処分も片付け110番にお任せください!

夏の楽しいひとときを彩る花火。しかし、その後の花火の処分にお困りではありませんか?特に、大量の花火やロケット花火、打ち上げ花火は、自治体の通常のごみ収集では対応が難しい場合があります。そんな時は、信頼と実績のある不用品回収業者「片付け110番」にお任せください!お客さまで事前に水に浸しておくなどの処理は一切不要です。ご希望の日時に合わせて回収スケジュールを調整します。土日祝日も対応可能です。お電話またはウェブサイトから簡単にお問い合わせいただけます。スタッフが丁寧に対応し、見積もりをお出しします。スタッフが現地に伺い、安全かつ迅速に花火を回収・処分しますので、お客様は家でお待ち頂くだけでOKです。安全・迅速・確実に花火を処分し、安心して快適な生活をお過ごしいただけるよう、力になります!
片付け110番の不用品回収サービスについては、コチラをご覧ください。