親が亡くなると、自宅や賃貸の部屋に残された物をどう整理すればいいのか、気が重くなる方は少なくありません。実家の大きな家財や思い出の詰まった品々をどこから手をつけるか迷うことが多いものです。
相続人同士の話し合いが必要なケースもあり、感情面の負担も大きくなるため、計画的に取り組むことが大切です。遺品の中には手続きに必要な書類や価値のある品が含まれる場合もあるので、じっくり進めるための準備が欠かせません。
本記事では、親の遺品整理をスムーズに進めるための基礎知識から具体的な手順、業者を利用する際のポイントまでを詳しく解説します。これから遺品整理を始めようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
親の遺品整理とは?基本の考え方

まずは、親の遺品整理がどのような位置づけなのか理解するところから始めましょう。
親の遺品整理とは、亡くなった親の持ち物を分類し、必要な品を選別・保管のうえで不要な物を適切に処分する作業のことを指します。大切な形見から手続きに欠かせない書類、家具家電など、多岐にわたる物が変わらずそこに残されるため、想像以上に手間と時間がかかります。
整理の際には、法的に相続権のある人たちが主体となって行うことが基本です。相続人全員で話し合い、作業を分担することでトラブルを避け、効率よく整理を進められます。
また、単なる物理的な片付けだけでなく、家族としての思い出に向き合う重要な機会でもあります。時間をかけ、できるだけ感情面のケアも行いながら取り組むと後悔の少ない形で整理を終えられるでしょう。
親の遺品整理は誰が行う?相続人全員で進める重要性
法的には親の遺品整理は相続人に権利と責任があります。相続人が複数いる場合は、全員で協力して話し合いながら整理を行うことが望ましいでしょう。
例えば、特定の遺品に思い入れがある人や、遠方に住む人も含めて合意を得ることで、後から「勝手に処分した」といった誤解が生じにくくなります。負担を皆で分担できる点も大きなメリットです。
特に遠方から来る人がいる場合は、日程調整や作業負担をどう割り振るか事前にしっかりと話し合いましょう。円滑な進行が家族全体の心の負担も軽くします。
遺品と不用品の違い〜感情面の整理も必要〜
遺品整理では、想い出や故人らしさが詰まった品物をどこまで「必要」とするのか判断が難しい場合があります。写真や手紙、日記などは、捨てることに抵抗感を覚える人も少なくありません。
それでも作業を進める上では、必要品か不要品かを区別しなくてはなりません。例えば貴重品や必要書類は必ず取っておき、価値のないものや物理的に保管が厳しい荷物は処分または他の親族への引き取りを検討しましょう。
時間をかけて感情面も整理することが大切です。不要と判断した品でも手離しに抵抗を感じる場合は一時保留とし、後で再度判断する方法も有効です。
遺品整理を始めるタイミング:持ち家・賃貸で変わるポイント

住居形態によっては、早めの行動が必要な場合やゆっくり進められる場合など状況が異なってきます。
実家が持ち家の場合は、退去期限などがないため比較的ゆとりをもって進められます。一方、賃貸住宅や老人ホームなどが住居だった場合は、家賃負担を考え早めに整理して契約解除を行わなければなりません。
タイミングを誤ると家賃や管理費の支払いなど、金銭面での負担が増加するリスクがあります。余裕がなければ、専門業者などのサポートも検討しましょう。
親が住んでいた地域の自治体によっては粗大ごみの収集日が限られている場合もあるので、いつから作業を始めるとスムーズに進むか逆算して計画を立てることをおすすめします。
持ち家の場合:落ち着いて作業するための目安
持ち家の場合は、しばらくそのままにしておいても料金が発生することはありません。実家の片付けは物量が多いこともあり、心に余裕をもって取り組める点が大きなメリットです。
ただし、あまりにも時間が経過すると気力が失われたり、親族同士の都合がつかなくなったりする恐れもあります。落ち着いて取り組める時期を見計らい、計画的に進めるのが理想です。
持ち家だとしても税金や光熱費の基本料金が発生する場合は、その分の負担も考慮して整理のスケジュールを決めましょう。
賃貸の場合:契約解除や家賃負担を考慮した早めの対応
賃貸住宅や施設の部屋を引き払う際には、契約解除の手続きを行う必要があります。通常、部屋を空け渡すまでの家賃や管理費がかかるため、一日でも早く整理を開始したほうが費用を抑えられます。
また、空け渡し時期を延長すると違約金が発生する場合もあるため、親族で協議しながらスピーディに進めることが大切です。作業期間が短縮できないほど遺品が多い場合は、業者の一括サポートを検討する選択肢もあります。
早めの準備が結果的に家族の負担を減らすことにつながるため、賃貸の遺品整理では迅速さを念頭におきましょう。
3ヶ月以内がひとつの目安?意外に進まない実情
一般的に、賃貸か持ち家かを問わず、親の遺品整理には3ヶ月ほどの期間を目安に計画を立てることが多いです。書類探しや相続手続きの並行作業などもあるため、かなりの時間を要します。
実際には感情面での整理が進まず、思っていたより長期化するケースも少なくありません。特に写真や思い出の詰まったアイテムの扱いは慎重を要します。
3ヶ月以内にある程度の目処をつけ、その後も残った細かい品の仕分けを継続していくと、精神的な負担も抑えながら作業を進めやすくなります。
親の遺品整理をスムーズに進める事前準備

まずは相続人との連絡体制を整え、必要な道具やスペースを用意することが重要です。
遺品整理の作業量は思った以上に多く、複数人で同時に作業を進めることもあるため、事前の打ち合わせが欠かせません。誰が、いつ、どの部屋を担当するのかといった役割分担も決めておくとスムーズに進みます。
合わせて、現場で必要となる道具や運び出し時の導線などを確認しておくと無駄な時間を省けます。スケジュール作成の際には、自治体のごみ収集日や粗大ごみの処分受付状況なども織り込んでおきましょう。
遠方に住む親族や忙しい人には、オンラインで進捗を共有する方法もあります。互いに負担なく進めるために、小さな情報も含めてこまめにやり取りすることを意識しましょう。
相続人・親族との事前連絡:トラブル回避のカギ
意外とよくあるのが、必要な連絡が行き届かないまま整理に着手し、後から「勝手に処分された」といったクレームに発展するケースです。特に形見や思い出の品は人によって大切さが異なるものです。
開始前に全員へ連絡を行い、貴重品や思い入れの強い物などの希望を確認しておきましょう。デジタル遺品(パソコンやスマホのパスワードなど)も、専門業者の協力が必要かどうか検討しておくと後の手間が減ります。
事前連絡で合意が進めば、作業当日は無駄なトラブルに時間を取られることなく、効率よく整理に専念できます。
現状の下見とスケジュール作成
最初に、家や部屋全体をざっと確認して遺品の量や種類を把握しましょう。見落としがちな押入れや物置、クローゼットの奥などに荷物がまとまっている場合も多いです。
下見の段階で、おおよその作業日数や人手の必要性が見えてきます。例えば大型家具が多いのであれば、運び出しに複数人の協力や車両の手配が必要になるでしょう。
スケジュールは、相続手続きの進捗も考慮に入れて柔軟に修正できるように余裕を見て組むと、途中で慌てず落ち着いて進められます。
必要な道具・作業スペースの確保
実際の整理作業では、仕分け用の箱やごみ袋、軍手・マスク、カッターなどさまざまな道具が必要です。埃が多い場所や害虫が出る可能性もあるので、防塵メガネや長袖の服装を用意しておくと安心でしょう。
また、整理した品を分別・保管しておく作業スペースを確保することを忘れないでください。散らかった状態で仕分けを行うと、何がどこに置いてあるか分からなくなり、時間が余計にかかってしまいます。
スペースが不足している場合は、段階的に部屋ごとに整理を進めたり、レンタル倉庫などを一時利用する方法も検討できます。状況に応じて柔軟に対応しましょう。
親の遺品整理の具体的手順:仕分けから処分・供養まで
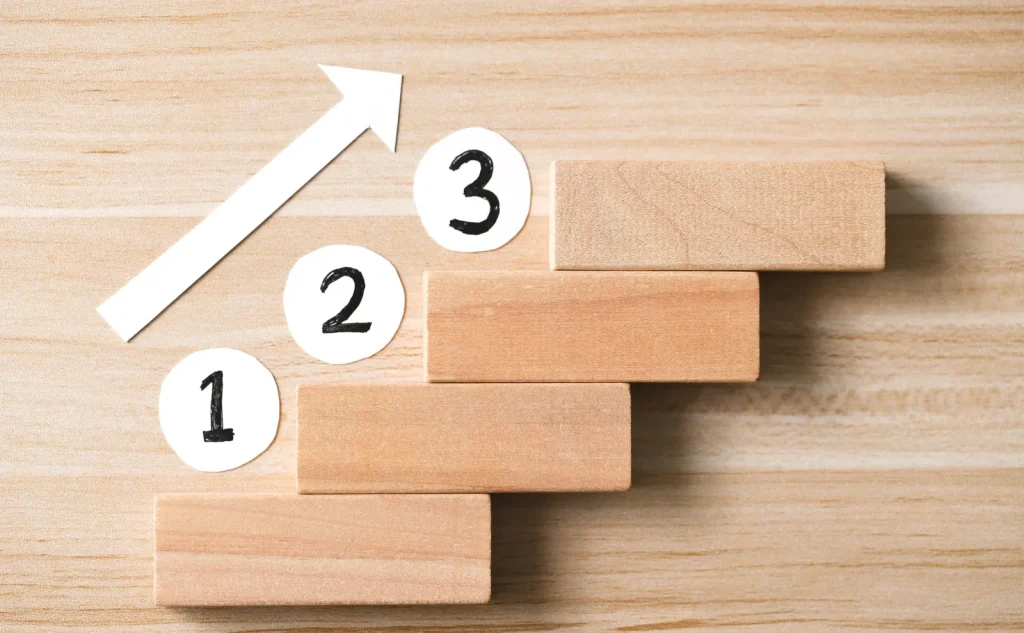
ここからは実際の整理作業をどのように進めるか、流れを追って見ていきましょう。
遺品整理の最初のステップは、何よりも重要書類や貴重品を探し出すことです。後の相続手続きなどに関わるため、まずは重点的にチェックを行いましょう。
次に、家具家電をはじめとした大きな器物から小物まで仕分けを進めていきます。残す物、売却や寄付が可能な物、捨てる物に分類すると効率的です。
最後に、写真や手紙などの供養が望ましい遺品があれば、専門の寺院や業者に依頼して敬意を持って処分・供養するようにしましょう。
まずは貴重品・重要書類を念入りに探す
印鑑や通帳、保険証書などの重要書類は意外な場所に保管されていたりします。タンスの奥や引き出し、封筒の束などを見逃さないように一つひとつ確認しましょう。
重要書類の中には相続手続き、年金や生命保険の受け取りに関するものなど、家族にとって必要不可欠なものが含まれています。初期段階でしっかり確保できるかが後々の手間に大きく影響します。
全ての部屋を見渡すとともに、書き込みのあるノートや手帳にもメモやパスワードなどが残されている可能性があるため、丁寧にチェックしてください。
遺品の仕分け:残す物・売る物・捨てる物
親族や相続人全員で相談して、遺品を大まかに3つのカテゴリに仕分けます。残す物、売る物、捨てる物に分けることで判断の整理がしやすくなります。
思い出のあるものでも、形として残す必要があるかどうかや、保管スペースとの兼ね合いなどを考慮しながら決めることがポイントです。使わない家電や古い家具などはリサイクルや廃棄を前提に検討するケースもあります。
複数人で作業をする場合は、共有スペースにマークやメモを貼り、誤って捨ててはいけない物を明示しておくと、トラブル防止につながるでしょう。
処分方法の選択肢:自治体回収・リサイクル・業者依頼

不要になった物や供養が必要な遺品などは、内容に合わせて適切な処分方法を選びましょう。
素材や品目によっては、自治体で粗大ごみとして回収してもらえるケースも多く、比較的コストを抑えられます。一方で買取できる物はリサイクルショップなどを利用すれば費用面でメリットがあるはずです。
ただし、形見や写真、一部の遺品に関しては供養を検討することが望ましい場合があります。遺品供養を受け付けている寺院や専門業者に相談すると安心です。
遺品整理専門業者に依頼すれば、分別や処分先の手配までまとめて行ってくれるため、時間と労力を節約できます。状況や費用を比較しながらバランスよく選択しましょう。
地域の粗大ごみ・不用品回収を活用する
自治体の粗大ごみ回収を利用すれば、処分費用を抑えられる場合が多く、比較的経費を軽減できます。回収日時の指定や大きさ・重さに関する規定があるため、事前に自治体のホームページなどで確認しましょう。
家財道具の多くが粗大ごみの対象となりますが、一部の電化製品は自治体回収では手続きが異なる場合があります。家電リサイクル法に対応した処理方法が必要となるため注意が必要です。
自分で搬出できない場合は、自治体指定の業者や有料回収なども視野に入れ、重い家具や大量の廃棄物があっても対応できる体制を整えてください。
買取やリサイクルショップを利用して収益化
まだ使える家電や家具、美術品、貴金属などはリサイクルショップや買取専門店に引き取ってもらうと費用の足しになる可能性があります。
状態が良ければ思った以上の買取価格がつくこともあるため、大量に捨てる前に一度査定を依頼してみる価値は十分にあるでしょう。
オークションサイトやフリマアプリなどを利用して売却を試みる方法もありますが、手間がかかる分、整理と同時進行で行うのは大変かもしれません。時間と労力を考慮しながら最適な方法を選んでください。
供養や形見分けが必要なものの手配
故人が大切にしていた物や写真、手紙などは、ただ捨てるだけでは心残りになるケースが多いです。寺院や専門業者による供養を依頼することで、丁寧に故人を送り出すことができます。
お焚き上げなどの儀式を行ってくれるサービスや、遺品一つひとつに対して合掌して供養してくれる業者もあるため、親の思いを大切にしたい方は利用を検討してみましょう。
形見分けを行う場合は、誰が何を引き継ぐか明確にしておくことが大切です。後々のトラブルを避けるためにも、親族間で十分に意思疎通を図ってから品物を分配してください。
専門業者に依頼するメリットと費用相場

時間や労力の節約だけでなく、安全面や法令順守の観点からも専門業者の利用には大きな利点があります。
一度に大量の遺品を整理・処分しないといけない場合は、専門業者に依頼するとスムーズです。荷物の運び出しから掃除、リサイクルや供養の手配などをまとめて行ってもらえるため、時間的にも精神的にも負担が軽減されます。
また、事前に見積もりや作業内容を確認できるため、費用面でも安心して任せられるでしょう。業者によっては不用品の買取も行っており、処分費用を相殺できる場合もあります。
料金相場は部屋の広さや物量、立地、作業内容(仕分け・梱包・運搬など)によって大きく異なります。
◆ 1R・1K(単身者向けのワンルーム)
相場:3万円~8万円程度
作業時間は半日~1日ほど。家具や家電が少なめで、袋詰めなどが比較的少ないケースが多いです。
◆ 1DK・1LDK
相場:6万円~12万円程度
ワンルームに比べて家具や家電、収納品が増えるため、作業人数が2~3人になることもあります。
◆ 2DK・2LDK
相場:10万円~20万円程度
部屋数が増えることで仕分けや搬出に時間がかかります。階段作業やエレベーターなしの場合は追加料金が発生することもあります。
◆ 3DK・3LDK
相場:15万円~30万円程度
家族で住まれていたお宅では物量が多くなりがちで、大型家具や家電、衣類、本などの処分が必要になることが多いです。
◆ 4LDK以上(戸建て・ファミリータイプ)
相場:25万円~50万円以上
遺品の量も多く、庭や倉庫、物置の整理も必要になるケースがあります。場合によっては数日かけての作業となり、作業員4~6名体制になることもあります。
【費用に影響するその他の要因】
- 階数・搬出経路の状況(階段のみの建物やトラックまでの距離があると追加費用)
- 仕分けや梱包の有無(丁寧な仕分けを希望する場合は人件費が増加)
- 貴重品・リサイクル品の有無(買取が可能な場合、費用から差し引かれることも)
特殊清掃が必要なケース(孤独死などの場合、別途料金がかかる)
片付け110番で親の遺品整理を依頼された事例

実際の依頼例を見ることで、具体的な費用感や作業の流れをイメージしやすくなります。
片付け110番では、規模の大きな一軒家から賃貸のワンルームまで、あらゆる住居の遺品整理に対応しています。専門知識を持ったスタッフが迅速かつ丁寧に作業を行うため、多くの利用者から高い評価を得ています。
ケース(1)5LDK、実家、父他界のため遺品整理、384,500円






| 回収内容 | 遺品整理のご依頼 |
| 実際の作業料金 | 384,500円 |
| お客様のご要望 | 5LDK、実家。父の他界のための遺品整理。物は多い方です。ゴミ屋敷ほどではありません。最短見積もり希望。 |
まとめ:親の遺品整理を安心して進めるためのポイント

親の遺品整理では、事前準備や計画的な作業が何よりも大切です。
必要な連絡と役割分担をしっかり行い、作業をスムーズに進めるためのスケジュールと道具を整えることで、後々のトラブルを最小限に抑えられます。賃貸の場合は契約解除の期限に間に合わせる工夫も重要です。
感情的にも負担の大きい作業だからこそ、専門業者の利用や親族の協力を得ながら進めると安心でしょう。特に貴重品の捜索や供養品の取り扱いは、丁寧なチェックが必要です。
物理的な整理だけでなく、故人の想いを大切にした供養や形見分けを行うことで、気持ちの区切りをつけることができます。必要に応じて専門家へ相談しながら、無理なく遺品整理を終えましょう。
親の遺品整理のご相談も片付け110番にお任せ下さい

専門家の力を借りることで、安心とスピード、そして故人への思いを大切にする遺品整理が叶います。
片付け110番では経験豊富なスタッフが状況や要望を十分にヒアリングし、最適なプランをご案内しています。一括で仕分け・処分までサポートし、供養や買取の対応も可能なため、任せて安心です。
初めての遺品整理は何かと不安が付きものですが、プロのサポートを受けることでトラブルやストレスを大きく軽減できます。費用や作業内容について疑問がある方は、まずは問い合わせてみてください。
遺品整理は故人との思い出を偲ぶ大切な作業でもあります。ぜひ片付け110番に相談し、心に余裕を持って整理を進めてみてはいかがでしょうか。


