成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産や身上監護を手厚く守るための重要な仕組みです。成年後見人は被後見人に代わり財産を管理・処分する役割を担いますが、その行動には家庭裁判所の監督や適切な手続きが伴います。
本記事では、成年後見人が財産を処分する際に押さえるべき法的根拠や実務の流れ、そして居住用不動産を含むさまざまな財産を処分するための具体的なステップについて整理します。特に、居住用不動産の売却には必ず家庭裁判所の許可が必要になるなど、後見制度ならではの特徴があります。
さらに、相続財産や任意後見制度との関わり、空き家問題に直面したケーススタディなど、現場でよくある課題にも触れながら、成年後見人が効率的かつ適切に財産を処分するためのポイントを解説します。成年後見人として活動される方だけでなく、将来を見据えて制度を把握したい方にも参考になる内容です。
成年後見制度とは?基本的な仕組みと法的根拠
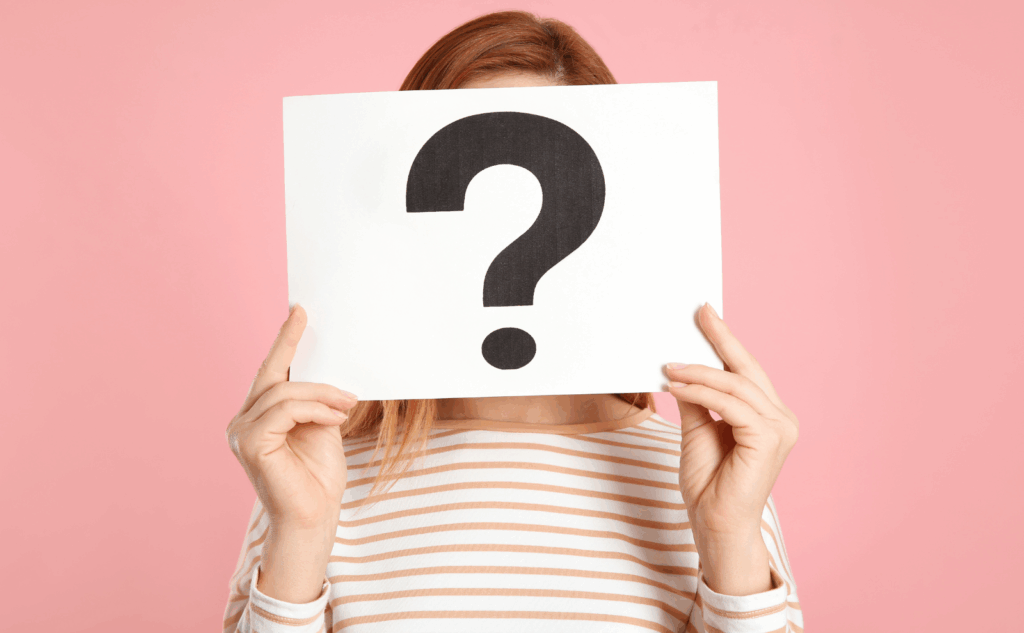
成年後見制度は、高齢者や障害を持つ方など、判断能力が低下した方を法的に支えるために整備された制度です。
この制度は、民法や成年後見制度に関する法律によって法的な枠組みが定められており、家庭裁判所が成人後見の開始や後見人の選任などを行います。判断能力が低下している方が不利益を被らないよう、厳格な監督のもとで財産管理や身上監護を行うのが特徴です。
申し立てが受理されると、家庭裁判所はその方の心身の状態に応じて、後見・保佐・補助のいずれかを決定します。成年後見人は、被後見人の利益を最優先とする前提のもと行動し、その結果などを定期的に報告する義務があります。
成年後見制度の設計上、財産の処分や重要な契約行為には厳しいルールが設けられており、特に不動産の売却や居住用物件の処分などでは、被後見人の生活や意思を最大限に尊重する視点が求められます。
成年後見人の権限と家庭裁判所の関与

成年後見人は、被後見人の財産管理や契約行為について幅広い権限を有しますが、その行使には家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。
被後見人の財産の運用や管理を任されることは大きな責任を伴います。後見人は被後見人のために、最適な形で財産を管理・処分する努力をしなければなりませんが、一定の範囲を超える重要な契約や処分には、家庭裁判所の承認、または監督人からの確認が求められます。
こうした監督体制の下、後見人が独断で被後見人にとって不利益な財産処分を行うことが防がれています。後見人は自分の利益のためではなく、あくまでも被後見人の生活や将来に役立つように判断しなければなりません。
特に居住用不動産を処分する際には、一層慎重な検討が必要とされます。被後見人にとって住まいは生活の基盤であり、後見人にはその処分の必要性や条件をしっかりと説明できる根拠が求められるのです。
財産管理における成年後見人の役割と責任範囲
成年後見人は、被後見人に代わって預貯金や不動産などの財産を管理する役割を担います。財産管理の範囲は広く、請求や支払いといった日常的な会計業務から投資運用の判断まで含まれる場合もあります。
ただし、その管理の目的はあくまでも被後見人の利益保護と生活維持であり、投資であれば慎重な検討が必要です。後見人個人の利益のために行動することはできず、常に被後見人が不利益を被らないよう配慮しなければなりません。
万一、不適切な財産管理を行った場合には責任を問われる可能性もあります。特に大きな財産処分では記録をしっかりと残し、家庭裁判所や関係者に説明できるような体制を整えることが求められます。
処分許可申請が必要となるケースと手続きのポイント
成年後見人が財産を処分するにあたっては、法的に家庭裁判所の許可が必要とされるケースがあります。代表的なものは居住用不動産や高額な財産の売却で、許可申請の際には被後見人の現状や、処分の必要性を証明するための書類を提出します。
特に居住用物件の処分許可申請では、家屋の評価額や売却理由、予定の売却金額の妥当性、被後見人の今後の居住先などの情報が必要とされます。これらを家庭裁判所に説明することで、被後見人にとって最善の判断であることを示します。
こうした手続きは慎重に行われるため、審理には時間がかかることが多いです。早めに司法書士や弁護士などの専門家と連携して準備を進めると、書類の不備なども防ぎやすく、許可までの時間短縮につながります。
居住用不動産の処分: 売却から残置物処分まで

被後見人が現在住んでいる、あるいは住んでいた家を売却するには、慎重な判断と家庭裁判所の許可が不可欠です。
居住用不動産は被後見人の生活に深く関わるため、財産処分の中でも特に手続きが煩雑になりがちです。被後見人の生活基盤であることから、処分しなければならない理由が明確であることが必要です。
売却が必要となる場合には、資金の用途や新たな住まいの確保についてもしっかりと検討しておく必要があります。被後見人のケア方針や、医療・福祉施設などへの入所計画も売却時の判断材料となり得るでしょう。
また、不動産の売却後には残置物の処分が必要な場合も多いため、タイミングを誤ると売却作業や契約手続きに支障が出る恐れがあります。そうした点を踏まえ、手続き全体を一括してスムーズに進めることが望まれます。
売却の流れとスケジュール例
まずは宅地建物取引業者に不動産査定を依頼し、資産価値を把握するところからスタートします。査定結果を参考に、売却価格の設定や販売戦略を立て、家庭裁判所へ許可申請の書類を準備します。
許可が下りた後は、本格的な売却活動に移行します。内覧や広告宣伝などを行い、買主が見つかったら契約条件や引き渡し時期を慎重に調整します。被後見人が転居中であれば、施設入所や新居への移動スケジュールとの兼ね合いを図る必要があります。
売却完了までには数か月以上かかることも珍しくありません。後見人としては、被後見人の生活費や医療費などに支障が生じないよう、売却の進行具合と被後見人の状況を常に把握することが大切です。
残置物処分の具体的な方法と注意点
居住用不動産には多くの家財道具や貴重品が残されている場合があります。家財の中には思い出の品や個人的な書類、場合によっては貴重な骨董品や宝飾品が含まれていることもあるため、安易に一括廃棄せずに仕分けを丁寧に行うことが重要です。
仕分けの際には、被後見人の価値観や思い出をできるだけ尊重します。どうしても判断が難しい場合や、大量に品物がある場合は専門業者への依頼を検討するとよいでしょう。依頼の際は、貴重品や個人情報が含まれる物品を丁寧にチェックしてもらう旨を伝えることが大切です。
残置物処分は売却に合わせて行うのが一般的ですが、タイミングを誤ると売却手続きや引き渡し時期に影響が出ます。あらかじめスケジュールを立て、不動産業者や専門の片付け業者と連携して効率よく作業を進めることが求められます。
非居住用不動産・動産の処分手順と注意事項
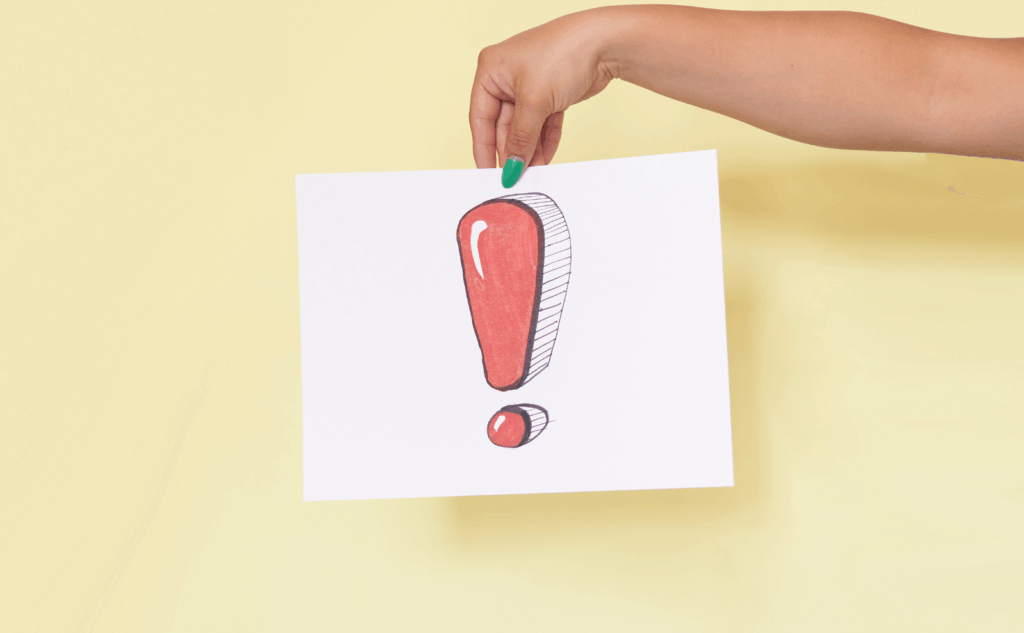
空き家や空き地などの非居住用資産を処分する場合も、後見人の判断と許可の範囲が重要になります。
非居住用不動産については居住用不動産ほど厳密な許可が必要ないケースもありますが、被後見人の利益に反しないかどうかを慎重に見極める必要があります。後見監督人の選任がある場合は、事前に処分の理由や必要性を説明する場面も生じます。
空き家の場合は管理コストや固定資産税の負担が大きく、収益が見込めないことから売却や活用を検討する後見人が増えています。売却を進めるにあたっては、市場価値を適切に把握し、被後見人にとって最適な処分価格を設定することが大切です。
動産の処分にあたっては物品の評価が難しい場合もあり、誤廃棄によるトラブルを避けるためにも、専門家に査定を依頼するなどの対策が必要です。
空き家・空き地といった不動産の管理・処分
空き家や空き地は放置すると老朽化や治安面での問題が生じる可能性があります。安全面や近隣トラブルのリスクを低減するためにも、早期に将来の方針を決めることが求められます。
?賃貸物件にするか売却するかなど、後見人はさまざまな選択肢を検討して、被後見人に最も利益があると考えられる方法を選びます。地域の不動産需要や物件の立地条件をしっかりと踏まえたうえで判断することが大切です。
家庭裁判所の許可が不要な場合でも、売却には契約内容や価格の正当性を示す書類が必要となる場合があります。後見監督人がついているケースでは、事前に相談しておくとスムーズな手続きにつながります。
動産処分に関わる費用やリスク対策
動産の処分では、処分費用のほか、搬出にかかる人件費や廃棄物の処理費なども考慮しなければなりません。古い家電や家具などを整理するには、専門の業者を手配するのが一般的です。
業者に依頼する際は、動産の買取りサービスを利用するか、完全に廃棄処分とするかを確認するとよいでしょう。思わぬ価値を持つ物品が含まれているケースもあるため、安易に一括廃棄は避けたほうが無難です。
また、搬出時に紛失や破損が起こるリスクがあるため、業者と保険契約の有無を含めて契約書を慎重に確認することが求められます。後見人としては、被後見人の財産価値を高める可能性を見落とさないよう注意が必要です。
相続財産と成年後見制度: 利害調整のポイント

相続が絡んできた場合、相続人の意思や家庭裁判所への報告など、財産処分に新たな調整要素が加わります。
成年後見人としては、相続財産の中に被後見人が所有権を持っていない財産が含まれる場合に注意が必要です。相続人それぞれの意向を聞き取りながら、被後見人の利益をいかに守るかが大きな課題となります。
相続財産の処理は通常、相続人間での協議や遺産分割協議書の作成を経て行われます。被後見人に具体的な意思表示が難しいケースでは、後見人が代わりに意見を取りまとめ、相続人に説明する場面も出てきます。
もし意見の対立が生じた場合、家庭裁判所に意見を求めるなど慎重に対処する必要があります。トラブル防止には初期の段階で協議の進め方を整理し、適宜法的なサポートを受けることが望まれます。
相続人との協議やトラブル防止策
相続人との協議では、被後見人に不利益とならないよう、後見人は公平かつ丁寧に情報提供を行い、話し合いをまとめていきます。特に財産全般の価値があいまいなままだと誤解を招きやすいので、現存する財産の評価を明確にすることが重要です。
協議をスムーズに進めるためには、専門家のサポートを得ながら遺産分割協議書を作成する方法が有効です。後で問題が起きないように細部まで合意を取りつけ、書面に残すことが大切です。
万が一意見が衝突した場合は、無理に合意を急がず、裁判所の調停や審判を視野に入れる必要があります。後見人は被後見人が不利益を被ることなく、相続人全体の合意点を模索する姿勢で取り組むことが重要です。
任意後見制度の活用と法定後見制度との違い

法定後見制度だけでなく、事前契約型の任意後見制度を活用することで、より柔軟な財産管理やライフプラン設計が可能です。
任意後見制度は、本人が判断能力を保っているうちに、自分が希望する信頼できる人と後見契約を結んでおき、将来の判断能力低下に備えるしくみです。法定後見制度が開始される前に、任意後見人としての権限や条件を細かく設定できることがメリットといえます。
法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選任しますが、その際に本人の意思がどこまで反映されるかは状況次第です。任意後見の場合は、契約を結ぶ段階で具体的な財産管理の方法などを協議し、本人の希望をより正確に反映することが可能になります。
ただし、任意後見契約を締結するには公正証書の作成が必要であり、契約締結後の管理内容についても注意深く検討することが望まれます。家族間での見解の相違を避けるためにも、専門家と十分に相談してから導入するのがベストです。
任意後見契約を結ぶメリット・留意事項
最大のメリットは、誰に後見人になってもらうかを本人の意思で決められる点にあります。これによって、財産の管理や処分をより納得のいく形で進めやすくなります。
契約にあたっては、公証役場で手続きを行い、必要書類を整える必要があります。契約書には、財産管理の範囲、報酬、任意後見監督人の選任などが明記されます。本契約が効力を持つのは判断能力が低下した以降になります。
留意すべきは、任意後見制度利用開始後の財産処分にも家庭裁判所の関与が及ぶケースがあることです。あらかじめ契約書で定めていない範囲の行為については、法定後見に準じた処置がとられることもあるため、事前に検討しておくことが重要です。
実例・ケーススタディ: 不動産売却と空き家処分
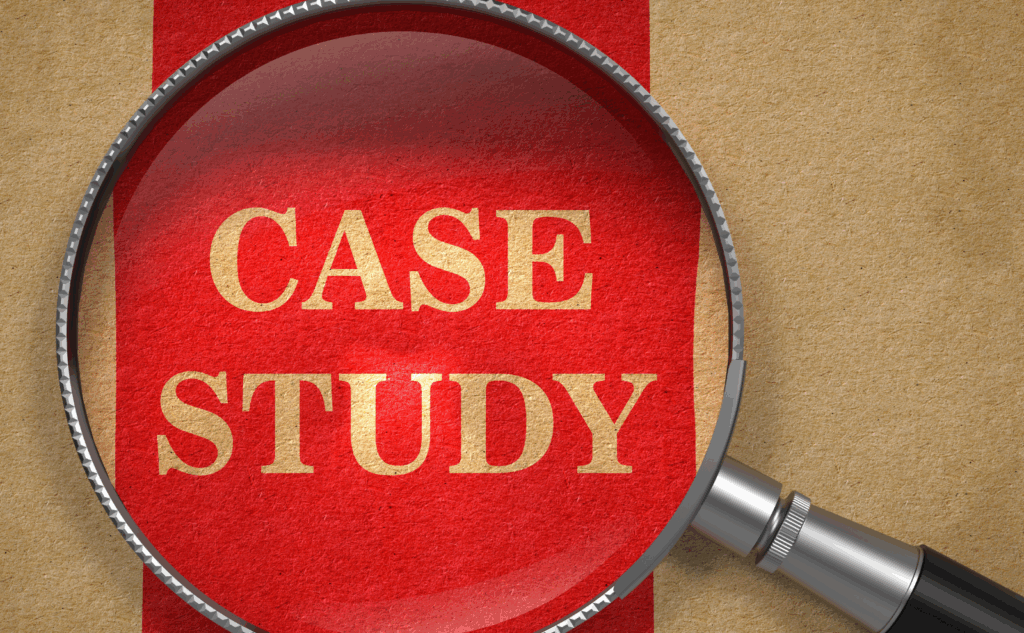
実際の事例を通じて、成年後見人が不動産売却や空き家処分をどのように進めるのか、その手順や留意点を見ていきます。
ケーススタディを活用することで、理論だけでは見えにくかった実務上のスケジュールや書類手続きの手間が具体的にイメージできます。例えば、被後見人が老人ホームに入所し、自宅が不要になったケースでは、売却価格の設定に加え、残置物の確認や搬出の手続きが必要になりました。
また、市場価値が低い空き家を売る場合、購入希望者が見つからないリスクに備えて、地域の不動産業者と連携して販売ルートを広げる工夫が重要です。売却できない間も固定資産税を支払う必要があるため、早期の処分を目指すことが多いです。
後見人はこうした状況において、家庭裁判所に計画書を提出し、十分な説明を行いながら売却の承認を得ることになります。最適なタイミングや方法を考慮することで、被後見人の利益を最大化し、トラブルを最小限に抑えることができます。
具体的事例から学ぶ財産処分の流れ
ある事例では、被後見人が施設入所を決定したため、空き家となった自宅を売却することになりました。後見人は予備調査として不動産の査定を行い、司法書士やケアマネージャーとも連携して処分する必要性と時期を検討しました。
家庭裁判所への許可申請時に提出する書類には、売却理由や生活再建計画などが含まれます。必要に応じて契約を仮押さえにしておく場合もありましたが、許可が下りる前に本契約を結ぶのは避けたほうが無難です。
最終的には、被後見人の生活費や医療費をまかなえる十分な売却金額で契約を締結し、家財道具は専門業者に依頼して安全に処分しました。この事例からは、綿密な準備と関係者との連携がスムーズな財産処分の要となることがわかります。
売却時によくあるトラブルと回避策
不動産売却でよくあるトラブルのひとつに、境界問題が挙げられます。明確な境界線が不明確なまま取引を進めると、後に隣地所有者との争いに発展する恐れがあるため、測量や境界確認を事前に行うことが重要です。
また、買主のローンが通らないなどの事情で売却契約自体が白紙になるケースもあります。そうした場合に備え、仮契約時点で手付金の扱いを決めておくなどの対策を講じ、後から混乱しないよう準備しておく必要があります。
さらに、被後見人が売却に対して否定的な感情を抱く場合も考えられます。可能な限り本人の意思や気持ちを尊重し、後見人側がきちんと目的とメリットを説明することで、納得してもらいながら手続きを進めることが望ましいです。
成年後見人による財産処分まとめ・総括

ここまでの内容を総合的に振り返り、実務で役立つポイントを改めて整理します。
成年後見人が行う財産処分には、被後見人の利益を第一に考え、家庭裁判所の監督を受けながら慎重に手続きを進める必要があります。居住用不動産以外にも動産や相続財産など、さまざまな財産の形態があり、それぞれに適した手順や注意点を押さえることが大切です。
財産処分を進める際は、許可申請に求められる書類やスケジュール、第三者との利害調整など、事前準備が大きな鍵を握ります。そのため、司法書士や弁護士と連携しながら、後見監督人や家庭裁判所の意見を十分に考慮するプロセスが欠かせません。
また、任意後見制度を活用することで、より柔軟な財産管理ができる可能性もあります。後見制度を一括りにせず、被後見人の状況や家族の意向に合わせて最適な選択肢を検討し、安心で納得できる財産処分を実現することが望まれます。
残置物処分・空き家片付けは片付け110番にお任せ下さい

家財道具や貴重品を含む不用品の片付けは、専門の業者に依頼することで、安全かつ迅速に対応できます。
居住用・非居住用物件ともに、長年放置されていた家財や可動しなくなった家電、処分方法がわからなくなった古い家具などの片付けでお困りの場合、専門の片付け業者と連携すれば負担を大幅に軽減できます。
片付け110番では、丁寧な仕分けと再利用可能品のリサイクルなど、環境と個人情報の管理を考慮した作業を行うため、安心して任せられます。成年後見人としては、被後見人の大切な思い出やプライバシーを大切に扱ってくれる業者を選ぶことがポイントです。
専門業者の力を借りることで、膨大な残置物の分類や買取り査定なども効率よく進められ、売却手続きや引き渡しスケジュールをスムーズに管理できます。後見人としても、時間や手間を節約しつつ確実な財産処分ができるので、安心感が大きいでしょう。



