空き家を相続すると、老朽化や税金、管理コストなど様々な問題が発生する可能性があります。そこで重要になるのが、空き家をどう処分・活用し、リスクを減らすかという点です。
近年は少子高齢化や都市部への人口集中などにより、全国的に空き家の数が増加傾向にあります。今後、相続による空き家がますます増えることが予想されるため、早めの対策が必要です。
本記事では、空き家を相続した際に知っておきたい基礎知識や具体的な処分方法、税制優遇制度などを詳しく解説します。住宅の状態や家族構成、経済状況などに合わせて最適な選択をするためのヒントを提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 空き家を相続したときに押さえておきたい基礎知識
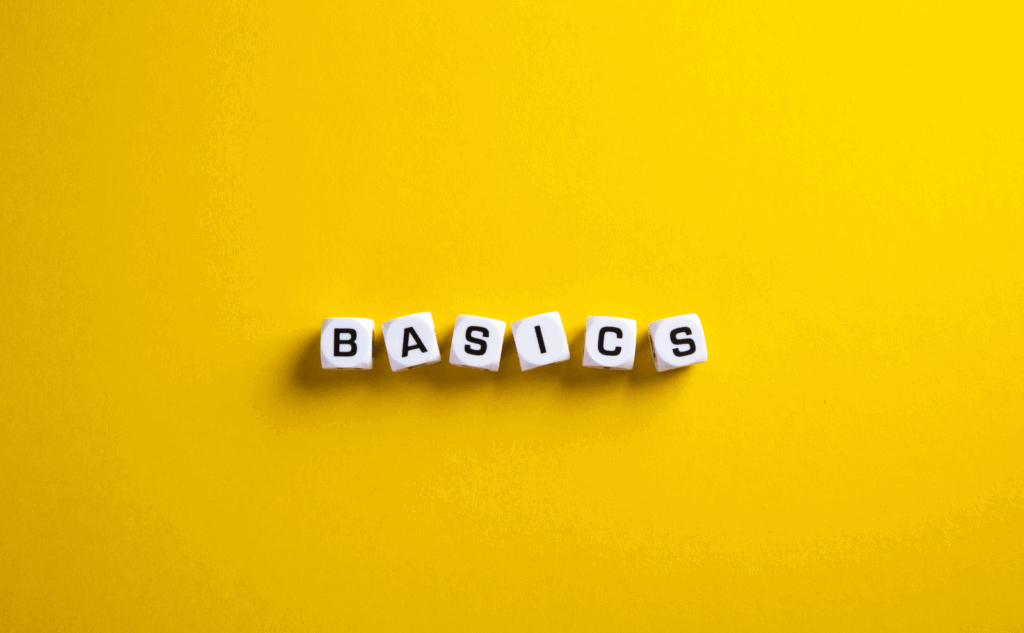
まずは空き家相続についての基本事項を整理し、必要な手続きや影響を把握しておきましょう。
空き家を相続するときは、単に建物を受け継ぐだけではなく、税負担や建物の維持管理といった責任も伴います。特に古い住宅の場合、老朽化によるリスクや近隣への影響も無視できません。
空き家の管理を怠ると、倒壊や不審者の侵入といった安全面の問題が発生する可能性があります。放置してしまった結果、自治体から特定空き家に指定されるケースもあり、固定資産税が増額されるリスクがある点にも注意が必要です。
相続した空き家を活用するか処分するかは、物件の立地や市場ニーズ、家族の意向によって最適解が異なります。正確な査定や専門家のアドバイスを得て、後悔のない選択をするように心がけましょう。
1-1. 空き家とは?法的定義と社会的背景
空き家とは、居住も使用もされていない家屋のことで、法的には建築基準法などで取り扱いが異なる場合があります。しかし一般的には、基本的なライフラインが使用されておらず、誰も住んでいない建物を指すことが多いです。
社会的背景としては、少子高齢化によって家の相続が増え、一方で活用のない建物が増加しています。都市部では不動産需要が高くとも、郊外や地方では需要が低く、買い手がつかないケースも珍しくありません。
国や自治体は特定空き家に対する施策を強化しており、問題のある空き家を放置し続けると法的なペナルティが科される場合もあります。空き家を放置すると地域の治安や景観を損ねるため、早めに行動することが大切です。
1-2. 名義変更や相続登記の必要性
空き家を相続した場合、まず必要となるのが相続登記です。相続登記をしなければ、所有者が曖昧になり、将来の売却や活用時に手続きが複雑化します。また、名義変更が完了していないと固定資産税の納税通知書が前所有者に届き、不要な混乱が生じることもあります。
相続登記は原則として期限が設けられていませんでしたが、法改正によって将来的には義務化される方向にあります。手続き自体が煩雑に感じられる場合は、司法書士などの専門家に依頼することでスムーズに進められます。
名義変更を怠ると、数年後に急いで売却を検討したとき、登記手続きの遅れが足かせになる可能性があります。余計なトラブルを回避するためにも、相続が発生した時点で早めに手続きを行いましょう。
1-3. 相続税への影響と小規模宅地の特例
相続税を算定するうえで、空き家の評価額や土地の広さなどが課税額を左右するポイントになります。特に市街地にある土地は評価額が高くなる可能性があり、場合によっては税負担が大きくなります。
小規模宅地の特例は、被相続人が居住用として使用していた宅地等に適用されることで、評価額を最大80%減額できる制度です。しかし、遺産分割の方法や使用実態など、細かい条件を満たさなければ適用を受けることはできません。
適用の可否は状況によって異なるため、一度専門家や税理士に相談してみるのがおすすめです。特例をうまく活用できれば、大幅な相続税負担の軽減につながる可能性があります。
2. 空き家を放置するリスクとデメリット

空き家を放置してしまうと、想像以上に多くのリスクが生じます。
実家を相続したものの、遠方住まいなどで手が回らず放置してしまうケースは珍しくありません。しかし、管理されない空き家は建物の老朽化を加速させるだけでなく、倒壊リスクや治安の悪化を招く要因にもなります。
近隣住民とのトラブルが発生すれば、魅力的な土地だとしても売却時の印象が悪化し、資産価値の低下を招きかねません。また自治体から行政指導を受け、撤去や修繕の命令が出る可能性もあるため、長期放置は大きなリスクといえます。
こうした問題を回避するためにも、空き家を所有している場合は早い段階で状態を把握し、処分方法を検討する必要があります。賃貸や売却などの具体策を踏まえながら、費用や手間を最小限に抑える手段を見つけることが大切です。
2-1. 老朽化や倒壊リスクによるトラブル
古い建物は屋根や外壁、基礎部分などが雨漏りやシロアリ被害によって劣化する場合があります。これを放置すると、地震などの災害時に倒壊の危険性が高まり、近隣に被害を及ぼすかもしれません。
もし倒壊事故が起きた場合、管理責任を追及される恐れがあります。空き家であっても所有者には安全管理の義務があるため、必要に応じて修繕や解体などの対策を講じなければなりません。
定期的に建物の状態を点検することが基本ですが、遠方の場合は管理を他社に委託する方法も検討が必要です。万が一に備えた保険加入も、費用対効果を考えながら検討しておくと安心です。
2-2. 発生し続ける固定資産税・管理コスト
空き家を所有している間は、利用実態にかかわらず毎年固定資産税が課されます。建物が倒壊の危険を抱えていても、解体しない限り税負担が発生し続ける点は大きなデメリットです。
また、雑草の除去や建物の定期点検など管理コストも積み重なります。特に庭木の剪定やゴミの収集などが怠られると、近隣への影響や景観悪化の原因となり、苦情に発展することもあります。
こうした費用と手間を負担し続けるよりも、早めに処分の方針を固めるほうが合理的なケースは多いです。専門家のアドバイスを受けつつ、売却や賃貸などの具体的な計画を立てましょう。
2-3. 治安や衛生面での問題
空き家は外部からの侵入者にとって格好の場所になることがあります。不法投棄や不法侵入が増えてしまうと、一気に地域全体の治安が悪化する可能性があります。
さらに、通気や清掃が行き届かない家屋は湿気がこもり、害虫や害獣の住処になりやすいです。近隣住民からすると悪臭や衛生被害をもたらす迷惑空き家として認識され、苦情が増え、地域社会との摩擦が生じる恐れがあります。
こうした問題が深刻化すると、自治体から是正勧告や除去命令が下される場合もあります。空き家の所有者としては、地域の安心・安全を守るためにも、定期的に点検や清掃を行うなどの対応が求められます。
3. 空き家を処分する7つの方法

空き家の処分は複数の選択肢があるため、それぞれの特徴を理解して最適な方法を選びましょう。
空き家の処分方法は、大きく分けて売却・賃貸・解体・寄付・放棄などがありますが、それぞれにメリットとデメリットが存在します。個々の事情に合わせ、最適な方策を丁寧に検討することが重要です。
将来の資産形成を考えるなら、賃貸やリフォームでの活用も選択肢になります。一方で、早期に現金化したい場合は不動産会社による買取が効果的です。相続放棄を検討するケースもあり得ますが、手続きや家族間の合意が必要になる点には注意が必要です。
以下では、7つの代表的な方法を紹介します。それぞれの特徴を把握し、自分の状況にあった方法を見つけ、トラブルを最小限に抑えながら空き家をスムーズに処分・活用していきましょう。
3-1. 空き家のまま売却する
最もシンプルな方法は、現状のままで空き家を売却することです。リフォームや解体の費用をかける必要がなく、比較的手間がかからないのがメリットとなります。
ただし、建物の状態が悪い場合や立地条件によっては、買い手が見つかりにくいことも考えられます。また、売却価格が相場より低くなりやすい点には注意が必要です。
売却する際には、まず不動産会社に査定を依頼して相場を確認しましょう。複数社から査定を取ることで、より適正な売却価格の目安を把握できます。
3-2. 更地にして売却する
建物を解体して更地にして売却する方法は、建物の状態を懸念されることが少なく、買い手のニーズを広く取り込めるというメリットがあります。土地のみのほうが活用プランを立てやすく、新築などの需要を取り込みやすいのが特徴です。
ただし、解体費用が発生するため、売れるまでの初期コストを考慮する必要があります。解体費用は建物の構造や大きさ、立地条件によって大きく変動します。
更地にすると固定資産税が増額になるケースもあるため、売れ残った場合の税負担には注意が必要です。解体費用の補助金制度を利用できる場合があるので、自治体の情報を事前に確認しておきましょう。
3-3. 賃貸やリフォームで有効活用する
空き家をリフォームして賃貸物件として運用すると、長期的に家賃収入が得られます。特に立地が良い場合や住宅需要がある地域では、家賃収入が安定し、資産価値を維持しやすいメリットがあります。
一方で、改装費や空室リスク、入居者対応といった負担が生じます。また、賃貸経営には一定の知識や管理コストが必要ですので、初心者の場合は不動産管理会社を使うなどの対策が必要です。
老朽化が進んでいる建物では、大規模リフォームをすることで物件の魅力を高められます。ただし、費用対効果を十分検討してから決定することが重要です。
3-4. 不動産業者による買取を依頼する
とにかく早く現金化したい場合に有効なのが、不動産会社の買取制度です。売却活動を経ずに不動産会社に直接買い取ってもらうため、短期間で処分できる利点があります。
ただし、市場相場よりやや安い金額での買取になる傾向があります。さらに、築年数や立地、建物の構造によっては買取自体が難しいケースもあります。
買取を検討する際は複数の不動産会社に問い合わせ、見積もりを比較することが大切です。会社によって査定ポイントや得意とする地域が異なるため、思わぬ高値がつく可能性もゼロではありません。
3-5. 空き家バンクに登録する
自治体が運営する空き家バンクは、空き家と移住・定住希望者をつなぐマッチングサービスです。地方移住ブームなどの背景もあり、地域によっては活発に利用され、売却や賃貸の成功事例が増えています。
空き家バンクへ登録することで、新たな居住者や起業家、リノベーション希望者など幅広い層にアピールできます。また、自治体によっては手数料や補助が受けられる場合もあります。
ただし、物件登録や案内が自治体主導になるため、即効性にやや欠けることもあります。こまめに登録状況をチェックし、必要に応じて民間の不動産サービスと併用すると、成約の可能性が高まるでしょう。
3-6. 寄付やNPOへの無償譲渡
空き家を社会貢献に活用してもらう方法として、NPO法人や行政機関などに無償で寄付する手段があります。利用ニーズがあれば地域活性化の拠点や福祉施設などに転用される可能性があります。
ただし、相手方に受け取りのメリットがない場合は断られることも多く、必ずしも受け取りを前提としないことが重要です。建物の状態や立地条件が社会的利用に適さないケースもある点に留意しましょう。
寄付や無償譲渡は売却と比べて収益が得られませんが、長期的な管理コストや相続税などの負担を軽減できる場合があります。公益性と経済性を総合的に考えて検討しましょう。
3-7. 相続放棄も選択肢になるのか?
空き家相続であまりにも費用負担が大きい場合、相続そのものを放棄するという手段も考えられます。相続放棄をすれば、名義や税金、管理責任から完全に解放されます。
しかし、相続放棄は他の遺産もすべて放棄することになるため、他に財産があった場合も含めて受け取れません。また、家庭裁判所での手続き期限が相続開始を知った日から3か月以内と短いことにも注意が必要です。
相続放棄した後に思わぬ財産があったとわかっても取り戻せません。慎重に情報収集し、空き家を含めた総合的な相続資産全体を吟味したうえで判断しましょう。
4. 借地権の空き家を処分する際のポイント

借地権付き空き家の処分は通常の不動産と異なる手続きが必要となるため注意が必要です。
借地権の空き家は、建物が自分名義であっても土地の所有者は地主であるため、処分時には地主との協議が不可欠となります。借地契約の条件次第では売却や建替えの自由度が大きく変わることも多いです。
一般的な所有権物件と比べて流動性が低く、買い手がつきにくいといったデメリットがあります。その分、価格設定や交渉スキルが重要になるケースも多く、専門家のアドバイスがあると安心です。
手続きのミスや地主とのトラブルは長期化する恐れがあります。早期に借地契約の内容を確認し、必要に応じて書面で同意を取り付けるなど、慎重な進め方を心がけましょう。
4-1. 地主への連絡と借地契約の確認
借地権付き空き家の処分を検討する際は、まず地主との連絡が欠かせません。勝手に売却手続きを進めてしまうと、契約違反となりトラブルを招く可能性があります。
借地契約には期限や更新料、建物増改築の可否など、細かい取り決めが定められていることがあります。契約書を丁寧に読み込み、地主の権利や承諾が必要な場面を正確に把握しておきましょう。
地主と円滑にコミュニケーションが取れない場合は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談するのも一案です。第三者の専門家を介在させることで、客観的な情報整理ができるようになります。
4-2. 借地権の売却・同時売却・買い取りの選択肢
借地権付き建物を売却する場合は、建物と借地権をセットで売却(借地権譲渡)するほか、地主に借地権を買い取ってもらう方法があります。地主が買い取りに応じてくれると、処分は比較的スムーズです。
ただし、地主への承諾料や名義書換料が発生することが多く、費用面の考慮が必須となります。地主の同意を得られないと、事実上の売却が困難になる可能性があるのも注意すべき点です。
同時売却とは、建物と土地を一括で売却することで、地主と買主との三者間で契約をまとめる形になります。利害調整が必要ですが、実現すれば買い手がスムーズに手に入れられる点で魅力があります。
4-3. 更地返還や賃貸活用などの判断基準
借地契約によっては、更地にして地主へ返還することが義務付けられている場合があります。この場合、建物を解体せずに売却するのは難しくなるでしょう。
賃貸物件として活用する選択肢もありますが、その際にも地主の承諾が必要となる場合が一般的です。家賃収入を見込む場合は、契約期間や更新料など、長期的な収益シミュレーションが欠かせません。
いずれの選択肢も、地主との良好な関係がスムーズな処分の鍵となります。借地契約の法律面に知見のある専門家に相談しながら、時間をかけて検討することをおすすめします。
5. 相続土地国庫帰属制度の概要と注意点

国に土地を引き取ってもらうことができる制度が創設されましたが、要件や費用など紐づく内容を把握する必要があります。
この制度は、相続後に土地の管理が難しい場合に、一定の条件をクリアすれば国に帰属させることができる仕組みです。老朽化した建物がある場合は先に解体が必要など、実際に利用するにはさまざまな要件を満たす必要があります。
国庫帰属の手続きを行うと、以後の固定資産税や維持管理費から解放されるメリットがあります。しかし、土地の状況によっては申請が却下されることもあり、必ずしも誰でも活用できる制度ではありません。
国による審査には時間がかかり、加えて手数料や事務コストも発生します。制度を使うかどうかは、他の売却・譲渡手段と比較検討したうえで判断するのが賢明です。
5-1. 国への引き取りが可能になる条件
相続した土地が一定の要件を満たした場合に限り、国庫帰属制度を利用できる可能性があります。要件は、境界が明確であることや、土壌汚染などの問題がないこと、建物などの撤去が済んでいることなど、多岐にわたります。
また、土地が急傾斜地など管理が著しく困難な場所でないかも審査されます。条件を満たさなければ帰属申請が拒否されるので、事前の確認が重要です。
制度の利用を検討する際は、自治体や専門家に相談し、申請書類の準備を慎重に進める必要があります。スムーズに進めるためにも、余裕を持ったスケジュールを組んでおきましょう。
5-2. 制度利用のメリットとデメリット
メリットとしては、維持管理の手間や固定資産税を将来的に支払わなくて済む点が挙げられます。手続きが完了すれば、相続人の金銭的・時間的負担を軽減できる可能性があります。
一方で、審査手数料がかかるほか、建物の解体費用をすべて自己負担しなければならないなど、利用にあたっては大きな出費が発生します。また、申請が通らない場合もあるため、確実性が高いわけではありません。
他に売却や寄付などの選択肢がある場合は、費用対効果を比べて結論を出すことが大切です。特に不動産が売却可能な立地であれば、そちらを優先したほうが利益を得られるケースも少なくありません。
6. 空き家の売却時に活用できる税制優遇・特例
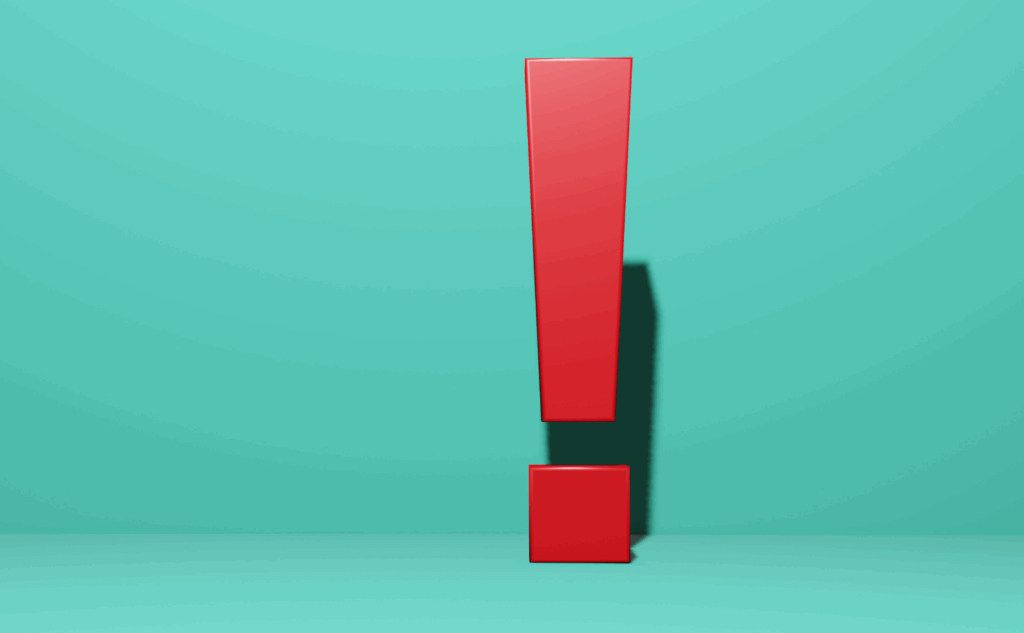
売却による譲渡益が生じる場合、税制優遇や特例を適用できる可能性があります。
空き家を売却して譲渡所得が発生すると、課税対象になります。そこで活用したいのが各種の特例や優遇です。特例を知らないまま売却してしまうと、余分な税金を支払うことになりかねません。
マイホームとして利用していた場合は3,000万円特別控除をはじめとした制度がありますが、他にも「空き家に係る譲渡所得の特例」など、近年の税制改正で追加された優遇措置が存在します。
優遇を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。建物の築年数や利用状況など、条件をクリアしているかどうかを確認してから売却を進めると、最終的な手取り額が大きく変わります。
6-1. 3,000万円特別控除の適用要件
居住用財産を売却した場合に利用できる3,000万円の特別控除は、広く知られる制度ですが、相続した空き家でも適用できるケースがあります。ただし、被相続人がもともと住んでいた家であり、一定期間空き家となっていないことなど、いくつか条件があります。
要件を満たしていれば、売却益から3,000万円が差し引かれ、課税対象額を大幅に抑えられます。ただし、複数の不動産を同時期に売却した場合や、すでに特例を適用している場合は制限がかかることもあるため慎重な確認が必要です。
控除の適用可否によって譲渡所得税の額は大きく変動します。税理士や不動産会社と連携し、手続きを正しく行うことで、より多くの利益を手元に残すことが可能です。
6-2. 空き家に係る譲渡所得の特例と令和5年税制改正
「空き家に係る譲渡所得の特例」は、被相続人が居住していた家屋を一定の条件のもと売却した場合に譲渡所得を大幅に減らせる制度です。対象となる築年数や家屋の状態など、厳格な要件が定められています。
令和5年の税制改正により、特例の対象期間や適用条件が調整される可能性があります。制度更新のタイミングを逃さず、最新情報に基づいて手続きを行うことで、想定外の税負担を避けることができます。
空き家の売却に際しては、こうした特例だけでなく他の減税措置も併せて検討することが重要です。複雑な内容なので、実際に活用する際には税理士などの専門家に相談するのが安全です。
7. 空き家の処分にかかる費用と補助金

解体費用やリフォーム費用は、物件の状態や社会情勢によっても変動します。
空き家を処分する際、解体費用やリフォーム費用は大きな出費となることが少なくありません。木造なのか鉄筋コンクリート造なのか、建物の構造によって解体工事のコストは異なります。
また、電力会社の引込線や浄化槽の撤去など、付帯工事が必要な場合もあり、費用はさらに高額になることがあります。リフォームに関しても、老朽化の程度が大きいほど費用はかさみます。
一方で、解体やリフォームに対して自治体が補助金を出しているケースも多々あります。要件や上限額は自治体ごとに異なるため、事前に公式サイトや窓口を確認し、申請漏れのないようにしましょう。
7-1. 解体費用・リフォーム費用の相場
木造住宅の解体費用は、延床面積1平方メートルあたり数万円が目安とされますが、地域や業者によって幅があります。鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート造)は重量があり、運搬・処分費も上乗せされるため、さらに高額になる傾向があります。
リフォーム費用は、内装の張り替えだけでなく、水回りや断熱性能の改善など多岐にわたります。部分的な改修にとどめるのか、スケルトンリフォームを行って全面改修するのかによって総額は大きく変わります。
実際に支払う費用は業者の見積もりや物件の状況次第です。複数の業者から見積もりを取って比較し、詳細な内訳を確認しながら予算に合ったプランを立ててください。
7-2. 補助金や助成金の種類と申請方法
自治体によっては、空き家の解体費用や耐震補強に対する補助金を用意しているケースがあります。制度の目的は、危険な空き家の減少や地域の景観・安全向上にあるため、要件を満たせば支給を受けることができるでしょう。
申請には、見積書や写真、登記情報などの書類提出が必要になります。さらに、受付期間が限定されていることもあるため、タイミングを逃さないように注意が必要です。
助成金を活用すると、実質的な負担を大幅に抑えられますが、必ずしも全額がカバーされるわけではありません。補助金制度を利用する際は、自己負担額や申請手順をしっかり理解した上で進めましょう。
8. 空き家処分に関する手続きの流れと注意点
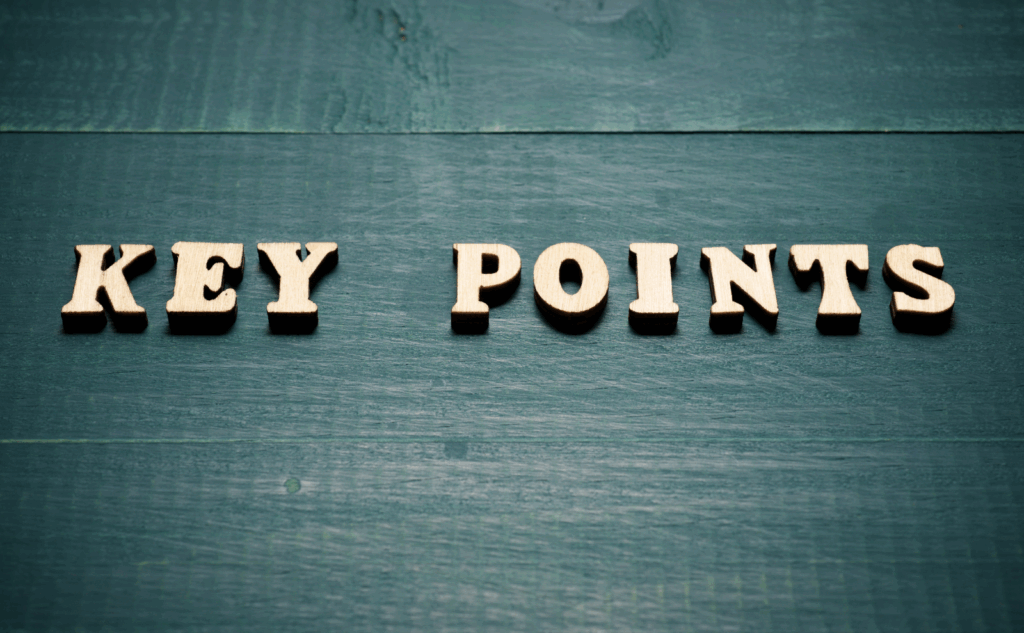
売却や譲渡など、空き家を処分するための実務的な手続きは複数のステップを踏む必要があります。
相続登記が完了しているか確認し、必要があれば早めに名義変更を済ませます。次に、不動産会社へ査定を依頼し、売却や賃貸の価格帯を把握しましょう。もし国庫帰属制度や寄付などを検討する場合も、早めに情報を収集しておくことが重要です。
買主が見つかったら、売買契約や重要事項説明などのプロセスに移ります。契約締結後は、残金決済と同時に物件を引き渡し、各種税金や諸費用の最終精算を行う流れです。
書類の不備や契約条件の確認不足があると、後々トラブルに発展する可能性があります。事前に必要書類をそろえ、専門家と連絡を密に取り合うことで、スムーズな処分を実現しましょう。
8-1. 相続登記から売却・引き渡しまでのプロセス
空き家を売却する際の基本的な流れは、まず相続登記の完了 → 不動産会社による査定 → 媒介契約 → 内覧・購入希望者の募集 → 売買契約 → 決済・引き渡しとなります。
相続登記が終わっていない場合は、売却手続きを進める際に名義不一致が生じ市区町村や買主側の手続きで混乱を招くリスクがあります。早めに相続登記を完了しておきましょう。
また、契約の段階では重要事項説明などで物件の状態をしっかりと開示し、トラブルを未然に防ぎます。必要書類の確認や印鑑証明など、細かい作業も多いため、時間に余裕をもって準備することが大切です。
8-2. 不動産会社・専門家との連携
空き家の売却や解体、税務手続きなどには専門的な知識が求められます。不動産会社や司法書士、税理士などと連携することで、適切な書類作成や税制優遇の活用など、多角的にサポートを得ることができます。
相続問題に詳しい不動産会社を選ぶと、相続登記の段取りや税制特例に関するアドバイスも期待できるでしょう。慣れない手続きを自力で進めるより、ミスを最小限に抑えることができます。
専門家との連携で費用は発生しますが、手続きがスムーズに進み、結果的に時間やトラブル対応の手間を節約できる場合が多いです。信頼できるパートナーを見つけるためには、複数の業者と相談・比較を行うことが大切です。
9. まとめ:空き家の処分は早めの対策が安心への近道

空き家の処分は、早急に対応することでリスクを最小化し、将来的な負担を減らすことができます。
相続した空き家を長く放置してしまうと、老朽化や固定資産税といった負担が重くのしかかります。さらに、地域の治安面でも問題が生じやすく、最終的には行政指導や倒壊リスクなど、深刻な事態に発展しかねません。
その一方で、早めに処分方針を整理することで、さまざまな選択肢が開けます。売却や賃貸化、寄付、相続放棄など、それぞれの方法に長所と短所があるため、専門家と相談しながら最適解を探すことができるでしょう。
今後、空き家をめぐる法整備や制度改正は継続的に行われる可能性があります。最新情報をキャッチしながら、家族や専門家と連携を取り、後悔のない空き家処分を目指してください。
10.空き家の処分は片付け110番にお任せ下さい
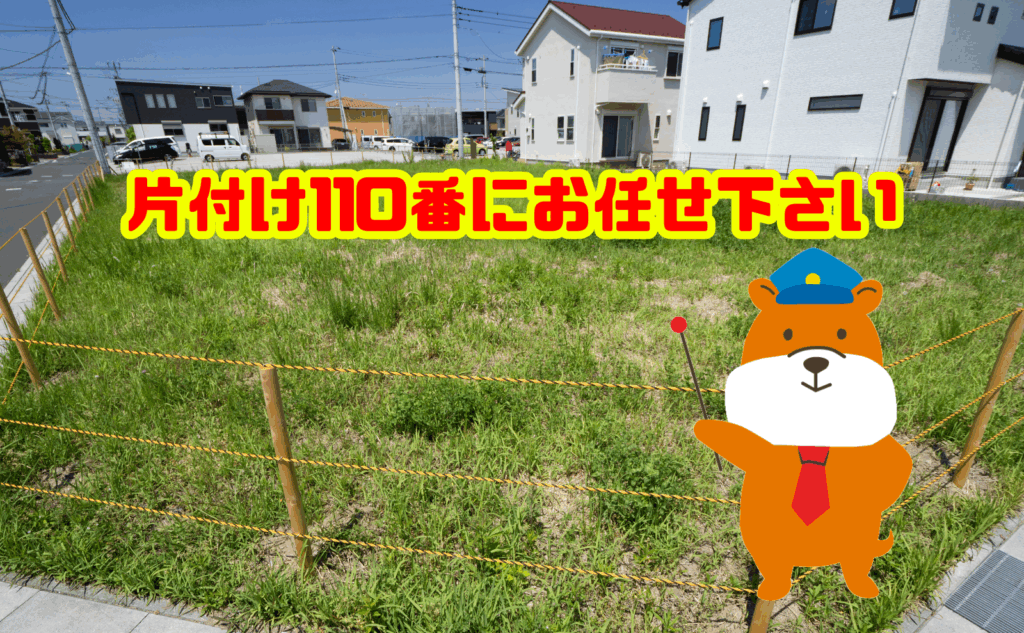
専門的な業務からサポートまで、空き家の処分をトータルでお手伝いしますのでお気軽にご相談ください。
片付け110番では、空き家のお片付けから遺品整理、解体やリフォームまで幅広いサービスを提供しています。遠方にお住まいの方にも対応し、必要に応じて専門家との連携も行いながらスムーズな処分を実現します。
物件の状態把握から売却サポート、手続き代行なども含め、ワンストップで対応可能です。面倒な作業を一括してお任せいただけるため、ご家族で負担を抱え込む必要がありません。
空き家の処分にはリスクやコストがつきものですが、早期の相談と計画によってトラブルを最小限に抑えることができます。まずはお気軽にお問い合わせいただき、最適な解決策を一緒に見つけましょう。


