相続放棄は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を一切相続しないという重要な手続きですが、放棄前後の財産処分の可否については慎重な判断が必要です。
本記事では、相続放棄の基本知識から具体的な手続きの流れ、絶対にやってはいけない処分行為や放棄後の管理義務について、網羅的に解説していきます。
相続放棄が可能な3つの選択肢(単純承認・限定承認との比較)

相続には、相続放棄、限定承認、単純承認の3つの選択肢があります。それぞれの特徴と相続人への影響を理解し、最適な決断を取ることが大切です。
相続放棄は、財産も負債も含めて一切を引き継がない選択肢です。限定承認は相続財産の範囲内で負債を負う仕組みで、すべての相続人が同意しないといけません。単純承認は手続きなしで自動的に相続人としての地位を継続するため、財産も負債も全て継承することになります。各方法のメリットとデメリットを比較したうえで、より最適な手続きに進むためには、最初に相続財産の種類や額を十分に調査することが重要です。
相続放棄とは?財産も負債もすべて放棄する手続き
相続放棄は、被相続人のプラス財産もマイナス財産も引き継がない手続きです。相続人としての地位を放棄することになるため、後から相続財産の存在がわかっても一切受け取ることはできません。原則として、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。期間を過ぎると原則相続放棄が認められず、事実上単純承認となってしまう可能性があるため、手続きは慎重に進めましょう。
限定承認とは?相続財産の限度で負債を引き継ぐ方法
限定承認は、被相続人の負債がプラスの相続財産を上回らない範囲で責任を負う方法です。負債をすべて支払ったあとに余った財産があれば相続できる点がメリットですが、手続きが複雑であり、すべての相続人が共同で申立てをしなければならないという制約があります。財産や負債の状況把握を十分に行わないまま限定承認を選択すると、後から思わぬ負債が見つかったときの対応に苦慮する場合があるため、専門家へ相談しながら手続きすることが大切です。
単純承認とは?すべての権利・義務を承継する選択
単純承認を行うと、被相続人の財産も負債もすべて引き継ぐことになります。特に何も手続きを行わない場合や、相続財産を処分する行為をしてしまった場合には法定単純承認が成立します。預貯金の引き出しや財産の売却といった行動は、後から相続放棄をしようとしても認められなくなる場合があるので注意が必要です。多額の負債が存在する可能性があるときは、相続放棄や限定承認を含めて慎重に検討する必要があります。
相続放棄の手続きの流れと期限
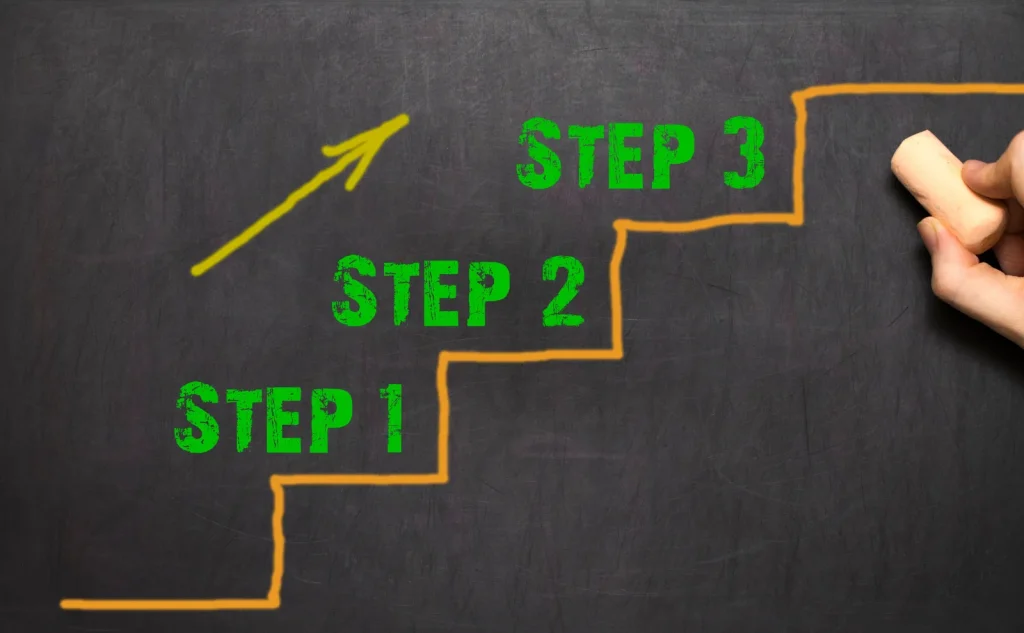
相続放棄は原則として、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てが必要です。期日を過ぎると相続放棄できない場合があるため注意が必要です。
スムーズな相続放棄を行うためには、まずプラス財産とマイナス財産の調査が重要です。預金通帳や借入金の契約書、クレジットカードの明細などを確認し、財産状態を大まかに把握しましょう。財産調査後、必要書類を準備し、出来るだけ早めに家庭裁判所へ相続放棄の申立て手続きを進めることが大切です。
家庭裁判所への申立て方法と必要書類
相続放棄の申立てには、相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本などが必要となります。該当の家庭裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。書類に誤りがあると再提出が求められる場合もあるため、不備がないように確認をしたうえで提出を行いましょう。
相続開始を知った日から3か月以内が原則
一般的には、亡くなった直後から慌ただしい状況が続くため、3ヶ月は意外と短い期間です。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てを行って期限延長を検討することも可能です。いずれにしても、相続放棄を決めたら早めに行動することが、手続きトラブルを避けるうえで重要になります。
相続放棄前後に絶対にやってはいけない財産処分

相続放棄を検討している段階での財産処分行為は、単純承認とみなされる可能性があります。どのような行為がNGとされるのかを理解しましょう。
相続放棄を行う前後の段階では、相続財産に対して勝手に手を加えないことが原則です。遺産を自由に使ったり、高価な品を勝手に売却するなどの行為は相続を承認したと判断されるリスクがあります。後に相続放棄を希望しても無効となる恐れがあるため、原則的に財産の取り扱いは最低限の保存行為程度にとどめておくほうが安全です。
預貯金の引き出し・解約や不動産の売却は要注意
故人名義の口座から預貯金を引き出したり、不動産を売却するなどの行為は法定単純承認とみなされる恐れがあります。特に、解約後に現金を受け取ってしまうと、事実上の相続財産の取得と判断される場合が多いです。相続放棄を考えている段階で、資金繰りや不動産の管理に困ることがあっても、軽々しく処分には踏み切らないように注意が必要です。
家財道具や車の処分が単純承認とみなされるケース
家の中の家財道具や車なども、明らかに経済的価値がある場合は処分しないようにしましょう。価値のある動産を売却したり譲渡したりすると、処分行為とみなされるおそれが高く、相続放棄の効力が失われるリスクが生じます。不要品を処分したいときは、相続放棄手続きが完了するまでは慎重に扱うことが重要です。
財産の隠匿・消費とみなされる具体例
相続財産を隠したり、勝手に使用する行為も重大なリスクを伴います。例えば、預貯金を自分の口座に移し替える、価値のある宝石や骨董品を無断で売却・換金するなどは、相続を受け入れたとみなされかねません。借金や税金の支払いに困っても、相続放棄を検討している場合は、安易に相続財産を使わず専門家に相談することが大切です。
相続放棄後に許される行為と管理義務のポイント
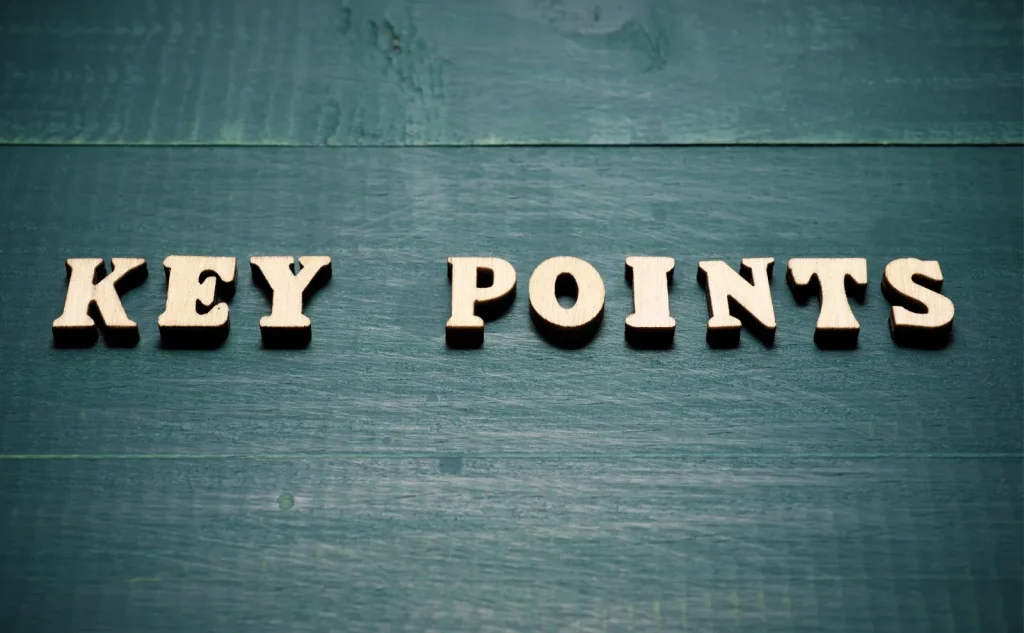
相続放棄をした場合でも、一定の範囲で認められる行為や管理義務があります。どこまでが許容されるのかを確認しておきましょう。
相続放棄をした後でも、財産が他の相続人や清算人に引き継がれるまでは最低限の保存措置を取る必要があります。特に、建物や土地などは放置すると周囲に迷惑がかかったり、損害が発生するおそれがあるため、必要な修繕や管理は行う必要があります。ただし、この範囲を超えた処分行為に踏み込まないようバランスに注意しましょう。
保存行為・短期賃貸借・社会通念上相当な葬儀費用
保存行為とは、雨漏りを防ぐための修繕や建物の最低限の管理など、財産の価値や状態を守る行為を指します。短期賃貸借は相続放棄後においても社会通念上認められており、必要に応じて一時的に事業者や第三者に貸し出すことが許されています。また、葬儀費用や墓地・仏具費用の負担も社会通念上必要な範囲内であれば、単純承認とみなされることは基本的にありません。
形見分けは財産価値の有無に注意
相続放棄後において思い出の品を形見分けする場合、経済価値の高い物品は処分行為とみなされる可能性があります。骨董品やブランド時計などは、形見分けのつもりでも実質的には資産価値の移転と判断されるかもしれません。親族間で大切な品を分ける場合でも、価値が少額であるかどうかを慎重に確認してから実行することをおすすめします。
相続放棄後の財産管理と相続財産管理人(清算人)の選任

相続放棄後も、残された財産を適切に管理する必要があるケースがあります。管理人の選任や財産の引き渡し手順を押さえましょう。
すべての相続人が相続放棄をするなどして管理する人がいなくなる場合、家庭裁判所が相続財産管理人や清算人を選任することがあります。これにより、残されている不動産や動産などの財産が誰の管理下にも置かれないまま放置される事態を防ぎます。清算人が選任されれば、相続財産に関する手続きや売却処分、債務の支払いなどを代わりに行うことが可能です。
財産の管理義務を免れるための実務手続き
相続放棄をした人は、いったん相続人の地位を失いますが、財産が他の相続人や管理人に引き継がれるまで最小限の管理義務を負います。管理義務を早期に解消したい場合は、速やかに他の相続人や家庭裁判所と連携して、財産の引き継ぎを進めることが重要です。必要に応じて書類や情報を整理し、正しく清算人へ引き継ぐことでトラブルリスクを低減できます。
管理組合や債権者からの要請があった場合の対応
マンションの管理費や固定資産税の支払いなど、相続財産にまつわるコスト負担を請求される場合があります。相続放棄後は相続人ではありませんが、財産管理を怠ると結果的に損害が拡大する危険もあります。そのようなケースでは相続財産管理人が対応するのが通常であり、実際に請求が来た際は家庭裁判所に管理人選任を申立てるなど、きちんとした手続きを踏みましょう。
相続放棄に関するトラブル事例と対処法

相続放棄を行う際には、家族間や債権者とのトラブルが生じることがあります。
相続放棄を決めた際にほかの相続人が不満をもらすケースや、そもそも相続財産の調査に協力してくれないケースがあります。また、債権者からの督促や、相続放棄を理解していない親族との対立など、複数のトラブルが生じる可能性があります。こうした問題は弁護士や司法書士といった専門家に相談し、法律上の根拠を整理しながら客観的な落としどころを見つけることが有効です。
まとめ・総括:相続放棄と財産処分で失敗しないために

相続放棄と財産処分は密接に関わり合いがあるため、双方を正しく理解することで不利益やトラブルを避けることができます。
相続放棄を検討するときは、まずは遺産の全体像を正確に把握することが必須となります。そして、相続放棄を成立させたい場合は、財産を処分しないよう意識的に気をつけ、早めに家庭裁判所への手続きを完了させることが重要です。いざ相続放棄後に財産管理が必要になった際には、管理義務の範囲や方法を正しく理解し、トラブルや責任問題をスムーズに解決できるように備えておきましょう。
不動産売却のお悩みは片付け110番にお任せ下さい

相続不動産の処分を検討中の方や、物件整理でお困りの方は専門家のサポートを活用しましょう。
相続不動産を売却するのか、そのまま保有するのかは慎重に判断すべきポイントです。特に相続放棄との兼ね合いが複雑な場合は、専門家が間に入ることでスムーズに手続きを進められます。最適な売却方法や管理手段を早期に確立して、不要なトラブルを避けることにより、相続手続き全体を円滑に完結させることが可能です。


